インフォメーション セイコーエプソン社製16ビットマイコン『S1C17M2シリーズ』6モデル、サンプル出荷を開始
24ピン小型パッケージで、小型家電やFA機器の5V動作にも対応する汎用マイコン
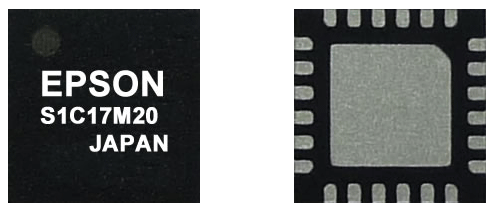 『S1C17M20』(SQFN4-24ピンパッケージ)画像(左)表面と裏面
『S1C17M20』(SQFN4-24ピンパッケージ)画像(左)表面と裏面
セイコーエプソン株式会社(社長:碓井 稔、以下エプソン)は、低消費電力16ビットフラッシュメモリー内蔵マイコンの新製品として、トースターなどの小型家電や、FA機器に搭載されるスイッチなどに適した『S1C17M20』を開発、このたびサンプル出荷を開始しました。同時に、シリーズ展開品『S1C17M21、S1C17M22、S1C17M23、S1C17M24、S1C17M25』もサンプル出荷を開始し、それぞれ月産20万個を予定しています。『S1C17M20』のサンプル価格は、SQFN4-24ピンパッケージで180円(税別)です。
エプソンでは、低消費電力を特長とした16ビットフラッシュメモリー内蔵マイコンで、小型家電だけでなく、モバイル機器などへの組み込み提案を行い、お客様からご好評をいただいています。今年6月には、5V動作対応(動作電圧 1.8~5.5V)「S1C17M3シリーズ」の量産を開始し、「S1C17ファミリー」のラインアップ拡充を進めています。
近年の家電製品は多機能化が進み、マイコンが処理する情報量は増加の一途にあり、マイコンの高速動作と小型化も求められています。
新製品『S1C17M20』は、当社マイコンでは端子数が最少のSQFN4-24ピンで、サイズは4mm x 4mmの小型パッケージをラインアップ。また、フロー実装※1に適したピン間隔0.8mmの『S1C17M21(TQFP12-32)』と、ピン間隔0.5mmの『S1C17M22(TQFP12-48)』を準備。あわせて、フラッシュメモリーを32kバイトにアップした『S1C17M23、S1C17M24、S1C17M25』も展開します。
さらに、電源回路や発振系端子、リセット端子を除いて、汎用入出力端子に設定できる仕様を実現しました。これにより、お客様製品の小型化や高機能化に貢献します。
エプソンは、省エネルギー、小型化、高精度を実現する「省・小・精の技術」により、お客様の製品のさらなる性能向上に貢献してまいります。
本製品の特長
1.お客様製品の部品点数や実装面積、ソフトウエア開発工数の削減に貢献するさまざまな回路を内蔵
- 内蔵発振回路は、16MHz、12MHzに加え、「S1C17ファミリー」では最速の20MHzも備え、お客様が任意に選択可能
- 自己書き換え可能な16kバイトのフラッシュメモリーと、2kバイトのRAM
- UPMUX(ユニバーサル・ポート・マルチプレクサ)機能搭載により、入出力端子の機能割り付けをソフトウエアで変更可能
- トレラント・フェイルセーフ対応I/O※2を設定しているため、電源電圧の異なる他機器とのI/O接続時、不要な電流が流れることによる消費電流の増加や回路故障を防止
- A/D変換器
- 3種類のシリアル通信機能
- 赤外線リモコン出力信号の生成回路
2. 電池寿命を延ばす低電圧および低消費電流動作
SLEEPモードでの消費電流は0.5 μAと低消費で、電源電圧は1.8~5.5Vまで対応しているため、産業用途から電池駆動の民生・IoT機器まで、広範囲なアプリケーション向けに採用することができます。
本製品の概仕様
| 型番 | S1C17M20 |
|---|---|
| CPUコア | 16ビットRISCプロセッサー +積和演算器、乗除算器 |
| フラッシュメモリー容量 | 16kバイト |
| RAM容量 | 2kバイト |
| 内蔵発振回路精度 | ±1%(12MHz動作時、動作温度10~40℃の場合) |
| 動作電圧 | 動作保証電圧範囲:1.8~5.5V |
| 消費電流 | SLEEPモード:0.5µA(標準値) 動作時:145µA/MHz (標準値) |
| 電源電圧検出回路 | VDD:28値(1.8~5.0 V)/外部電圧:32値(1.2~5.0 V) |
| 赤外線リモートコントローラー | 1チャンネル(応用としてELランプ駆動波形を生成可能) |
| A/D変換器 | 入力4本(12ビット逐次比較型) |
| タイマー | 16ビットPWMタイマー 2チャンネル 16ビットタイマー 4チャンネル ウォッチドッグタイマー リアルタイムクロック |
| シリアルインターフェース | UART:2チャンネル / SPI:2チャンネル / I2C:1チャンネル |
| I/O(入出力ポート数) | 最大 17本 うちUPMUX(ユニバーサル・ポート・マルチプレクサ)15本 |
| パッケージ | SQFN4-24pin(端子ピッチ: 0.5mm) SQFN5-32pin(端子ピッチ: 0.5mm) |
※1:溶かしたはんだの表層に基板の下面を浸すことによって、はんだ付けを行う方法。
※2:電源電圧の異なる他機器とのI/O接続時、不要な電流が流れることによる消費電流の増加や回路故障を防止するための機能。