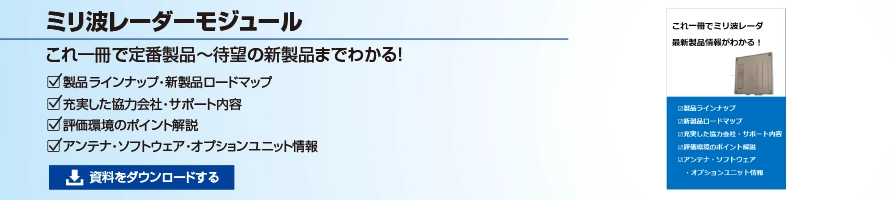ミリ波レーダーは自動車分野に活用されている|メリットや動作の仕組みも解説

「ミリ波レーダー」は、インフラ事業や製造業、農業、物流、情報システムなど幅広い領域で耳にすることの多い言葉です。また、最近では介護用システムでも利用されていることから、介護領域でも耳にする場合があるでしょう。
そこで本記事では、ミリ波レーダーに関する基礎知識や、そのメリットと弱点などを解説します。ミリ波レーダーが利用されている分野についても解説するため、関連事業に携わる人はぜひ参考にしてください。
お問い合わせはこちら
ミリ波レーダーのメリット
ミリ波レーダーを自動運転技術などに利用するのには、次のようなメリットがあります。
精度が高い
ミリ波レーダーは波長が短く、対象を高精度で検知可能です。特に距離分解能に優れており、距離が離れた物体の検出もできるため、高い精度が求められる車載監視レーダーなどにも利用されています。
環境に影響を受けにくい
ミリ波は環境の影響を受けにくいのも特徴です。霧・雨・雪が発生しているような場合でも、物体を検知できます。さらに、光の影響も受けにくいため、夜間や逆光がある場合など照度が著しく変化するようなシーンでも問題なく動作するでしょう。
小型化や軽量化が可能
アンテナのサイズは波長によって異なり、波長が短ければ、アンテナは短くて済みます。
ミリ波レーダーは波長が短く小型・軽量なため、搭載する製品の小型化・軽量化にも貢献します。
構造が単純
ミリ波レーダーは構造が単純で複雑な機構が必要ないため、比較的低コストで導入が可能です。またアンテナから電波を発信できる範囲が広く、装置に駆動部が必要ないため、耐久性が高いとされています。
ミリ波レーダーの弱点
ミリ波レーダーには次のような弱点もあります。利用の際には、このような弱点があることも理解しておくようにしましょう。
対象を検知できない場合がある
ミリ波レーダーは対象を高精度で感知できますが、対象が反射率の低い物体である場合は、検知することが難しくなります。また幅広い距離の対象を検知できる一方で、比較的近距離(センサー近傍)の検知を苦手としています。加えて、別のミリ波レーダーから影響を受けてしまう場合もあるため、場合によっては精度が落ちてしまうことが考えられます。
障害物に弱い
波が遮られた際に、波がその裏側に回り込むことを回折といいます。ミリ波レーダーは、他の周波数帯と比較して周波数が高く直線性が高いため回折しにくいとされています。そのため、照射したミリ波が障害物を十分に透過しない場合、その裏面を検知することはできません。
物体の形状や高所の検知が難しい
ミリ波レーダーは角度分解能が低いため、対象の形状を判断できません。送受信アンテナを多チャンネル化することで課題を解決することもできますが、コストの兼ね合いもあります。形状の測定は依然として他のセンサーに劣ると考えておくとよいでしょう。
自動車以外のミリ波レーダーの活用例
先述のとおり、ミリ波レーダーは自動車の自動運転技術に多く利用されていますが、その他の業界でもミリ波の活用が進んでいます。主な3つの例を紹介します。
産業機器
産業機器分野では、機械や人員の安全性を確保する目的で、ミリ波レーダーが利用されています。また小型で検知感度が良好なことから、利用の幅を広げる一因になっています。例としては、作業員の位置の検知や、機械の異常の発見、振動検査などが挙げられます。
ドローン
撮影やイベント演出など近年利用の場が増えつつあるドローンは、今後輸送業界でも活躍の見込みがあるなど需要が増えている一方で、安全性の確保という点で課題があります。
そこで、ドローンにミリ波レーダーを搭載することで、地面との距離を測定して飛行高度を維持したり、障害物を検知して衝突を避けるのに役立っています。
医療機器・介護
ミリ波レーダーは、医療分野でも活躍の場が期待されています。人の繊細な動きも検知できるため、非接触で人体の動きや睡眠状態、呼吸や心拍数などを推定する装置にミリ波レーダーの活用が検討されています。
また、高齢者の見守りシステムにも使用されており、人手不足が問題になっている介護業界での活用が進んでいます。