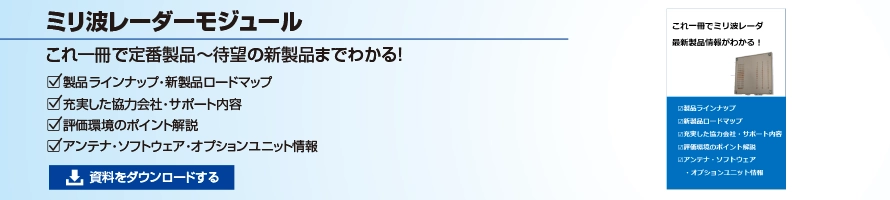ミリ波レーダーのデメリットとは?自動ブレーキの義務化に伴う背景や特徴も解説

自動ブレーキシステムは、車両に搭載されたセンサーやカメラが周囲の状況を検知し、衝突の危険性が高まった際に自動的にブレーキを作動させて事故を未然に防ぐ、あるいは被害を軽減するシステムです。
現在では、この自動ブレーキシステムは軽自動車やコンパクトカーにも広く普及しており、安全技術として欠かせない存在となっています。また、自動ブレーキには大きく分けて「カメラ方式」「ミリ波レーダー方式」「赤外線レーザー方式」の3種類があり、それぞれに独自の特徴やデメリットが存在します。
本記事では、「ミリ波レーダー方式」のデメリットに焦点を当て、その技術的な特性や課題について詳しく解説します。
お問い合わせはこちら
自動ブレーキの3種類
自動ブレーキは、搭載されるセンサーの種類によって主に「ミリ波レーダー方式」「カメラ方式」「赤外線レーザー方式」の3つに分類されます。以下では、それぞれの方式について詳しく解説します。
ミリ波レーダー方式とは
ミリ波レーダー方式は、ミリ波と呼ばれる電磁波を前方に照射し、その反射波を測定することで障害物を検知する技術です。追従機能(ACC)にも対応しており、高速道路などでの長距離運転に適しています。
しかし、物体の形やサイズを正確に識別することが難しく、特に歩行者や小さな物体を検知しづらいという課題があります。また、設置場所やシステム全体のサイズが大きくなる傾向があり、車両設計上の制約が生じることもあります。
カメラ方式とは
カメラ方式は、カメラを使用して障害物の種類(歩行者、車、看板など)や距離を識別する技術です。車線逸脱警告機能(LDW)を追加する際にも、追加ハードウェアが不要というメリットがあります。
一方で、逆光や悪天候(霧や吹雪)では視界が遮られ、システムが正常に機能しないことがあります。また、夜間はヘッドライトの照射範囲外の対象物を検知することが難しく、検出範囲に限界がある点もデメリットです。
赤外線レーザー方式とは
赤外線レーザー方式は、細く指向性の強い赤外線レーザーを照射し、その反射波を検知して障害物との距離を測定する技術です。照射距離は数十メートルと比較的短いものの、低コストでシステムのコンパクト化が可能という利点があります。また、レーザーの数を増やすことで障害物の輪郭をより正確に把握することができます。
しかし、検知エリアが狭いため、追従機能(ACC)には対応していません。それでも、衝突被害回避機能を低価格で提供できるため、軽自動車などコストを重視する車種に多く採用されています。また、暗い場所でも障害物との距離を検知できる点は優れていますが、距離が長くなると検出精度が低下するという課題もあります。
自動ブレーキの義務化について
2021年11月から、自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)の搭載が新型車に義務化されました。この義務化は、国産車と輸入車で対象期間が異なります。
国産車では、新型車は2021年11月から義務化され、継続生産車は2025年12月から義務化が開始されます。一方、輸入車については、新型車が2024年7月、継続生産車は2026年7月から義務化されることが決まっています。
なお、自動ブレーキ義務化の背景には、高齢運転者による事故の減少という目的があります。自動ブレーキの普及によって、安全運転サポート車(サポカー)のさらなる普及が期待されており、より安全な交通社会の実現を目指しています。
自動ブレーキを搭載した車の整備
自動ブレーキ技術をはじめとする先進運転支援システム(ADAS)の普及により、自動車整備のあり方も大きく変化しています。
以下では、自動ブレーキを搭載した車両の整備に関わる重要な制度である特定整備制度とOBD車検について解説します。
特定整備制度
2020年4月から施行された「特定整備制度」は、自動車の電子制御装置の整備も対象に含めた新たな制度です。従来のエンジンやブレーキなどの分解整備に加え、前方検知センサーやコンピュータの整備・改造も制度の対象となりました。
特定整備は、許可された業者のみが実施できることが義務付けられています。そのため、不適切な整備による事故やシステムの誤作動を防止し、自動車の安全性向上が図られています。
特定整備制度は、自動車のテクノロジーの急速な進化に対応し、走行安全性を確保するための重要な仕組みとして位置づけられています。
OBD車検導入
OBD車検は、車両に搭載された車載故障診断装置を用いて車両の状態を診断・検査するシステムです。2021年以降、新型乗用車、バス、トラックがOBD車検の対象となりました。
この検査では、指定のスキャンツールを使用して車種ごとの故障コードを読み取り、異常の有無を確認します。検査の合否判定は自動で行われ、その結果は専用サーバーに記録・保存される仕組みになっています。
OBD車検の導入により、運転支援装置や排気ガス装置に異常が発生した場合でも、簡単かつ正確にデータを検出し、安全性を確認することが可能になりました。
自動ブレーキのデメリット
自動ブレーキは、安全運転をサポートする便利なシステムですが、万能ではなく過信は禁物です。技術が進化しているとはいえ、完全に事故を防ぐものではありません。
例えば、自動ブレーキは歩行者や車両の色、急な飛び出しなどの特定の状況には対応できない場合があります。こうしたケースではシステムがうまく反応せず、衝突リスクが残ることがあります。
さらに、雨天や降雪、凍結路といった悪天候や特殊な路面環境では、自動ブレーキの精度が低下し、制動距離が変わることがあります。加えて、自動ブレーキ搭載車であっても、必ずしも事故を防げるわけではありません。
そのため、国土交通省はドライバーに対して安全運転の重要性を改めて呼びかけており、自動ブレーキを過信しないよう注意を促しています。
ミリ波レーダー方式のデメリット
ミリ波レーダーは、遠距離検知や高速走行時の安定性に優れた技術ですが、いくつかのデメリットも存在します。以下で詳しく解説します。
対象物以外の物体に遮られる
ミリ波レーダーは、対象物以外の物体に電波が遮られてしまうことがあります。特に電波の周波数が高いほど、物体による遮蔽の影響を受けやすくなります。
一方で、周波数が低い場合は回折しやすくなるため、エリア設計が複雑化し、運用に制限が生じることがあります。その結果、ミリ波レーダーはほかの技術と比較して、活用範囲が狭くなる可能性があります。
悪天候下で性能が低下する
ミリ波レーダーは悪天候に比較的強いとされていますが、極端な天候下では性能が低下することがあります。特に雨や雪などの環境では、電波が水蒸気や酸素分子に吸収され、飛距離が短くなったり、反射がうまく検出できなくなったりすることがあります。
そのため、悪天候時には障害物の検知が難しくなる場合があり、システム全体の安全性や信頼性が低下するリスクが伴います。
特定の物体に対する検知が難しい
ミリ波レーダーは、反射率が低い物体や小さな物体を検知することが苦手です。例えば、段ボールや細かな障害物などは反射が弱く、正確に識別することが難しい場合があります。また、水平分解能が低いため、物体の形状を正確に認識するのが難しく、特に小さな物体に対しては検知性能に限界があります。
さらに、近距離にある物体の検知も苦手とされており、超音波センサーやカメラとの併用が必要とされるケースが多いです。
まとめ
ミリ波レーダーは、自動ブレーキシステムにおいて重要な役割を果たす技術であり、高速走行時や長距離検知に優れた性能を発揮します。しかし、対象物以外の物体に電波が遮られやすいことや、悪天候下での性能低下、反射率の低い物体や小さな物体の検知が難しいといったデメリットも存在します。
自動ブレーキの義務化は、高齢者ドライバーの増加や事故防止を目的に進められましたが、システムに完全に依存するのではなく、ドライバー自身の安全運転が引き続き求められます。技術の特性を理解し、安全な運転環境を整えることが重要です。
丸文株式会社のミリ波レーダーは最先端技術を活用し、人検知や水位計測、レベルセンシング、車両検知、非接触バイタルサインモニタリング、距離測定を実現します。防犯設備やオフィス、駐車場、医療現場など、さまざまな環境で安全性と効率性を向上させる革新的なセンサーソリューションを提供し、業務の革新をサポートします。