はじめてのUSB [USB発展の歴史と基礎知識]
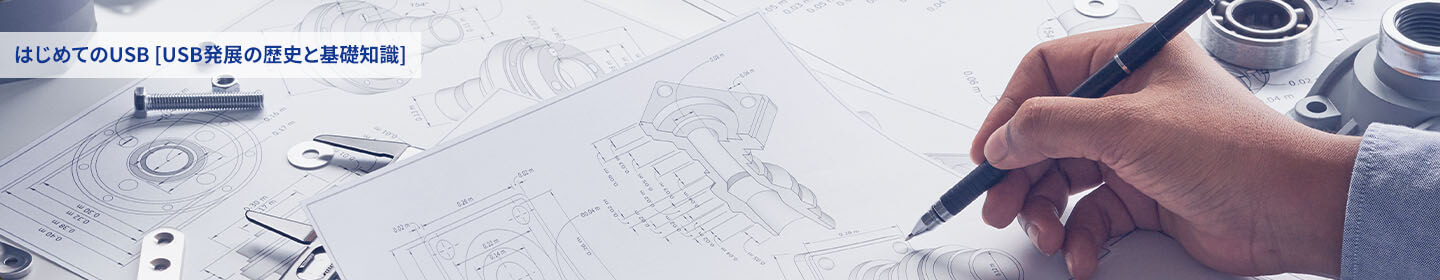
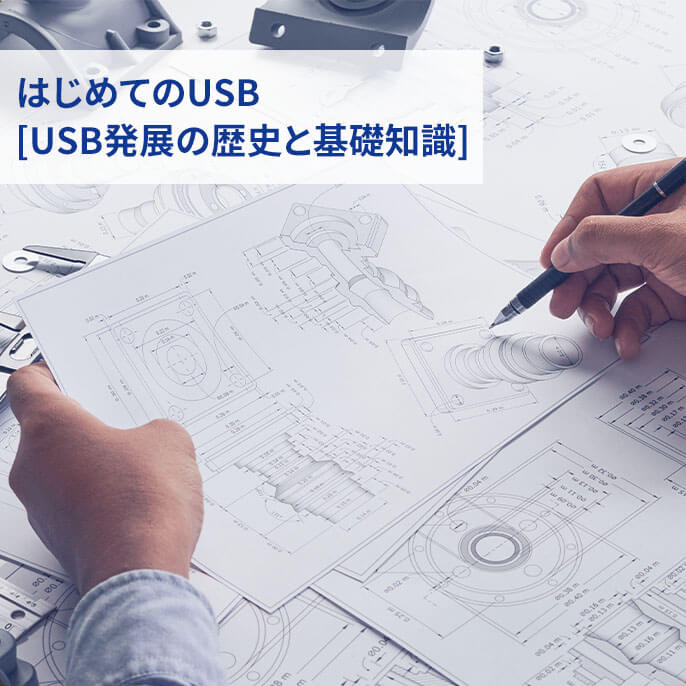
USB規格は20年以上積み上げてきた膨大な量の規格書から構成されています。この規格が策定された経緯、趣旨などの背景知識を得ることによって
規格の大枠を理解することができないかと考え、最初にUSB発展の歴史、次にUSBの基礎知識と用語解説を説明します。
内容は、USB Type-C™規格とUSB Power Delivery規格を理解するうえでベースとなる必要最小限のUSB 2.0/3.1の基礎知識と用語を説明します。
USB発展の歴史
現在までに策定されたUSB規格
USB440Gbps (Gen 3 x 2レーン)5~20V5A (max)2019年
| 規格名 | 最大転送速度 | 供給電圧 | 供給電流 | 規格策定年 |
|---|---|---|---|---|
| USB 1.0 | 12Mbps (Full-Speed) | 5V | 500mA | 1996年 |
| USB 1.1 | 12Mbps (Full-Speed) | 5V | 500mA | 1998年 |
| USB 2.0 | 480Mbps (High-Speed) | 5V | 500mA | 2000年 |
| USB 3.0 | 5Gbps (Gen 1) | 5V | 900mA | 2008年 |
| USB 3.1 | 10Gbps (Gen 2) | 5V | 900mA | 2013年 |
| USB 3.2 | 10Gbps (Gen 2x 1レーン) | 5V | 900mA | 2017年 |
| 20Gbps (Gen 2x 2レーン) | 5V | 1500mA | ||
| BC 1.2 | – | 5V | 1.5A | 2010年 |
| Type-C | – | 5V | 3A | 2015年 |
| Power Delivery | – | 5~20V | 5A (max) | 2015年 |
USB 1.0(1996年1月策定)およびUSB 1.1(1998年9月策定) 市場からの要求
USBによってどのような課題が解決できるか?
- 外付け周辺機器用インターフェイスをUSBに統一し、USBケーブルで様々な周辺機器が接続可能
当時のパソコン背面は、用途別に種類の異なるコネクタがたくさん並んでいました。
例)PS/2(マウス、キーボード)、シリアルポート(ダイアルアップモデム)、パラレルポート(プリンタ)等 - パソコンの電源を OFF にせず、周辺機器を追加可能(Plug and Play)
周辺機器を追加するために、パソコンの電源 OFF、周辺機器を接続後にパソコンの電源ONという手順が必要でした。
ターゲット市場
- パソコンの周辺機器。特にマウス、キーボード、モデムなど中低速周辺機器をターゲット。
競合するインターフェイス規格: IEEE1394
- 転送速度400Mbpsの高速インターフェイス
- USBと同様にPlug and Playに対応
- 主な用途
デジタル・ビデオ・カメラで撮影した運動会等の映像をパソコンに取り込んで編集
現在のスマートフォンへと進化を遂げる某社の初代音楽プレーヤーに採用
差別化要因
- 何でもつながるIEEE1394に対して、USBは、パソコンの中低速周辺機器用インターフェイスとして着実な一歩を踏み出しました。
パソコンは、5V出力が必須でバスパワーの周辺機器拡大がUSB普及の要因です。(競合規格は、バスパワーが必須の仕様ではありませんでした。)
USB 1.0(1996年1月)およびUSB 1.1(1998年9月)主な仕様
市場からの要求事項を元に技術仕様が規定されました。
- 規格上の最大転送速度
- 1.5Mbps: Low Speed、12Mbps: Full Speed
128kbpsを高速通信と呼んでいた当時としては12Mbpsは十分すぎる転送速度でした。
- 1.5Mbps: Low Speed、12Mbps: Full Speed
- バスパワー
- パソコンは5V出力必須、500mA以上供給可能
実際には1A程度の供給能力でした。 - 周辺機器によるバスパワーの利用は500mA以下
競合規格がバスパワーをオプション、出力電圧を8〜40Vと規定したことに対し、USBはバスパワーを必須、出力電圧を5V固定としたことで利用可能な周辺機器の種類が増え、後にUSBポートが充電用として利用され、USB Power Deliveryとして発展していきます。
- パソコンは5V出力必須、500mA以上供給可能
- コネクタ、ケーブル
- ケーブル長は最長5m、定格電流は1.5A以上
この1.5Aの規定が、後に充電規格USB Battery Charging Specificationの充電電流1.5A以下の根拠となります。
- ケーブル長は最長5m、定格電流は1.5A以上
- 接続構成
- 1台のパソコン(USBホスト)と周辺機器(USBデバイス)を接続
USBハブを利用して127台の周辺機器の接続が可能です。パソコン同士の接続、2台以上のパソコンが存在する接続構成、周辺機器だけの接続構成は禁止です。 - 接続構成の規定はUSB Type-C規格を理解するためにも重要なポイントです
- 1台のパソコン(USBホスト)と周辺機器(USBデバイス)を接続
USB 2.0 Market Requirements
USB 2.0が解決する課題は、パソコンの高性能化に伴う大容量データの高速通信です。
- ターゲット市場:大容量データを扱うパソコン周辺機器
- USB HDD, USBメモリ、CD/DVDドライブ
- デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ
- 音楽プレーヤー
- プリンタ、スキャナ
- 競合するインターフェイス規格:IEEE1394
- 差別化要因:バスパワーのUSBストレージ製品
USB 2.0が広まったきっかけは、2002年10月インテル社のチップセット(Intel ICH4)にUSB 2.0ホストコントローラが統合されたことです。
USB 2.0規格(2000年4月策定)主な仕様
転送速度480Mbpsの仕様が追加され、USB 1.1規格は、USB 2.0規格内に統合されました。
- 規格上の最大転送速度
- 480Mbps: High Speed(追加)
- 12Mbps: Full Speed、1.5Mbps: Low Speed
- バスパワー (USB 1.1規格と同一)
- パソコンは5V出力必須、500mA以上供給可能
- 周辺機器によるバスパワーの利用は500mA以下
- コネクタ、ケーブル
- USB 1.1規格と同一
- ケーブル長は最長5m、定格電流は1.5A以上
この1.5Aの規定が後に充電規格USB Battery Charging Specificationの充電電流1.5A以下の根拠となります。
- 接続構成 (USB 1.1規格と同一)
- 1台のパソコンと周辺機器と接続可能
- USBでパソコン同士の接続は不可
- USBハブを利用して127台の周辺機器の接続可能
- 互換性
- USB 2.0製品はUSB 1.1製品との互換性を維持
USB 3.0 Market Requirements
USB 3.0が解決する課題は、ギガバイトを超える大容量データの高速通信です。
ユーザーは一回のファイル転送でどのくらいの時間までならストレスを感じないかの調査を行いました。その結果、”threshold of pain”は90秒以内であることが判明しました。そこで27GBの動画を90秒以内に転送完了することを目標に設定しました。
- ターゲット市場
- 大容量データを扱うパソコン周辺機器
- USB HDD, USBメモリ、CD/DVDドライブ
- デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ
- 音楽プレーヤー
- プリンタ、スキャナ
- 大容量データを扱うパソコン周辺機器
- 競合するインターフェイス規格:SATA
- なぜUSB 3.0が最適な規格と言えるのか? (差別化要因)
- USBはPCの歴史で最も成功したインターフェイス
USB 3.0規格(2008年11月策定)主な仕様
- 規格上の最大転送速度
- 5Gbps: SuperSpeed
- バスパワー
- パソコンは5V出力必須、900mA以上供給可能
- 周辺機器によるバスパワーの利用は900mA以下
- コネクタ、ケーブル
- 新たなコネクタを規定、USB 2.0との互換性を維持
- ケーブル長は最長3m
- 物理層と信号線
- USB 2.0とSuperSpeed (5Gbps)の信号線は別
単純に通信速度を5Gbpsに上げただけでは目標とする実効転送速度まで上がりません。そこでデータ転送効率を上げるためにはUSB 2.0とUSB 3.xの伝送路を別にして、 USB 2.0と全く異なる通信仕様を策定する必要がありました。
- USB 2.0とSuperSpeed (5Gbps)の信号線は別
- 接続構成
- USB 2.0と同じトポロジ。
- ハブはUSB 2.0とUSB 3.0が混在した接続構成をサポート
- 互換性
- USB 3.0製品はUSB 2.0製品との互換性を維持
USB 3.0以降にリリースされた規格
- USB 3.1規格 2013年8月
- 5Gbpsの通信仕様に10Gbps仕様を追加
- USB Type-C規格 2015年
- コネクタ、ケーブルの小型化、上下、左右対称のPlug & Cable
- 5V 3A
- USB Power Delivery規格 2015年
- 5V~20V, Max 5A
- USB以外の通信(DisplayPort™, Thunderbolt™など)も可能
- USB 3.2 2017年
- 2組存在するSuperSpeed信号線を持つType-Cケーブルを使用することを前提
- 10Gbps x 2レーン、10Gbps x 1レーン、5Gbps x 2レーン or 5Gbps x 1レーン
- USB4™ 2019年
- Thunderbolt™ 3をベースとした通信仕様
- USB 3.2, DisplayPort, PCIExpress™ (オプション)をカプセル化して単一の物理層に統合する仕様
USBの基礎知識と用語解説
DFP (Downstream Facing Port) と UFP (Upstream Facing Port)
USBでは常にUSB Hostを中心に考えます。
- DFP (Downstream Facing Port)
- USB Host(上流)からUSBデバイス(下流)へのデータの流れ
- UFP (Upstream Facing Port)
- USB Device(下流)からUSB Host(上流)へのデータの流れ
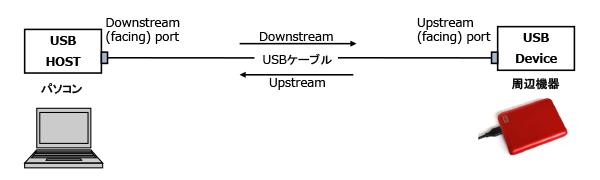
USBホストの役割
USB Power Delivery規格で登場するPower Role Swap、Data Role Swapを理解する上で重要な知識です。
- Power Role (Source)
- VBUS(5V)出力
- USB HostのVBUS(5V)のON/OFFを制御
- 外付けUSB Hubのダウンストリーム・ポートが出力するVBUSもUSB HostがON/OFFを制御
- Data Role (USB Host)
- USBデバイスに対してデータ転送の指示
USBケーブル
- Legacy USBケーブル(USB 2.0およびUSB 3.1)はA PlugとB Plugで構成されているので、必ずUSBホストとUSBデバイスの組み合わせで接続されます。
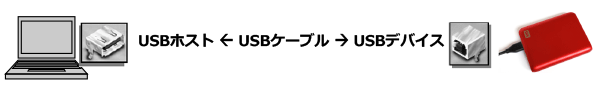
- Standard A PlugとStandard B Plug
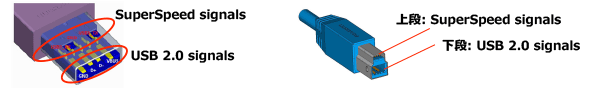
USB 2.0 / USB 3.1ピンアサイン
USB 3.1はUSB 2.0とSuperSpeedの信号線は別です。USB Type-C規格を理解するためにも意識すべきポイントです。
USBは元々マウス、キーボード等のために策定された規格であり、まさか5Gbps/10Gbpsの通信速度になるとは想定していませんでした。皆さんが使っているUSBマウスは何も動かしていない状態でもUSBホストから8msから32msの間隔でUSBマウスに対して、送るデータはないか常に問い合わせています。このようにUSB 2.0はデータ転送効率があまり良くない通信プロトコルであるため、単純に480Mbpsから5Gbpsに速度を上げても実行転送速度はあがりません。そこでUSB 3.0はUSB 2.0と全く異なる物理層を規定して信号線を別にしました。
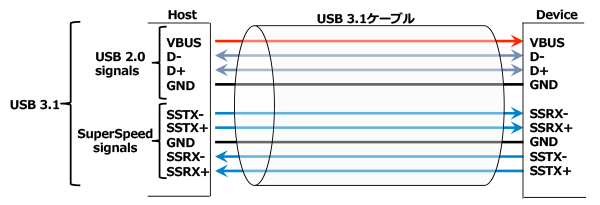
USB Physical Bus Topology
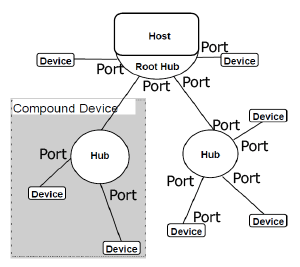
USBではすべてホストを中心に考えます。接続ポイントは、Portと呼びます。
●USBハブを使用して接続ポイントを増やすことが可能
●ハブは最大5段まで接続可能
●最大127台のUSBデバイス(USBハブを含む)を接続可能
●複数のUSBホストが存在してはならない
USB Logical Bus Topology
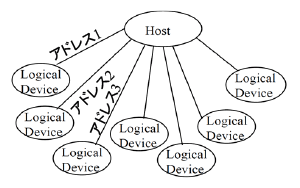
右図はLogical Bus Topologyです。
●論理的にはUSBホストとUSBデバイスが直接1対1で通信
●USBホストは各USBデバイスにアドレスを割り当てます
●USBデバイスは割り当てられたアドレスのパケットのみを受信
USB Battery Charging Specification 1.2規格 (BC1.2)
- USB 2.0のバスパワーの規定(500mA)を超える充電電流を実現するための規格
- USB Portable Deviceの急速充電
- 充電器の統一
- USB 2.0の問題点
多くのUSBホストはバスパワーの規定(500mA)を超える給電能力をもっていますが、Portable DeviceはUSBホストの給電能力を知る方法がありませんでした。 - 規格の主な内容
- Portable DeviceがUSBホスト又はUSBハブの給電能力を知る方法を規定。
- USB 2.0規格に影響を与えない範囲で、Portable DeviceとUSBホスト/USBハブ間で簡単なハンドシェークを行います。
- 仕様
- 最大7.5W (5V, 1.5A)
- USB Battery Charging Specification 1.2規格(BC 1.2)給電ポートの種類
- Standard Downstream Port (SDP)
- 従来のUSB2.0ポート(500mA)、USB3.0ポート(900mA)
- 従来のUSBポートとCDP, DCPと区別するためにSDPを定義
- Charging Downstream Port (CDP)
- 500mA以上の給電が可能なポート
- USBデータ通信が可能
- Dedicated Charging Port (DCP)
- 充電専用USBポート
- USBデータ通信が不可
- Standard Downstream Port (SDP)
BC 1.2採用例
- パソコン起動時はBC1.2 CDP (USBデータ通信 & 500mA以上の給電)
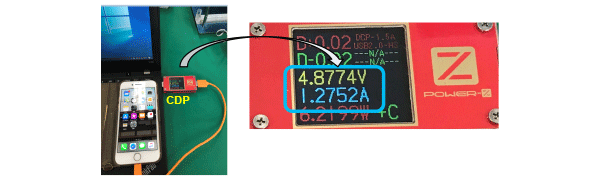
- パソコンサスペンド時はBC1.2 DCP (充電専用ポート)
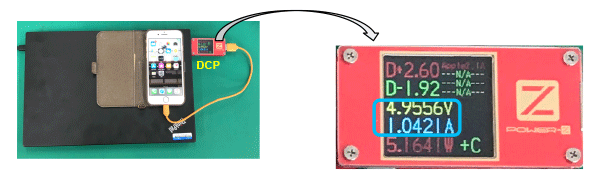
担当エンジニアからの一言
今回はUSB規格を大枠を理解するためのUSB発展の歴史と USB Type-C & Power Delivery規格を理解するための必要最小限の知識と用語を説明しました。USB規格を理解するために少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
