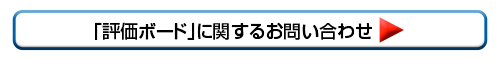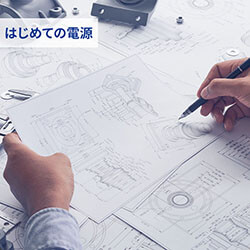スイッチング電源の問題について [リンギング対策 レイアウト編]


スイッチング電源の問題とは?
スイッチング電源のリンギングによる問題
スイッチング電源はスイッチング時間を高速にすることにより、スイッチング周波数の高周波化を実現しています。
その一方で、スイッチング時間の高速化によってリンギングノイズが発生しやすくなっています。
リンギングノイズが発生することで、ICの定格を超えたり他機器への悪影響が懸念されます。
リンギングノイズを減らすための対策はいくつかあります。
実際に基板を作成してリンギングを減らす方法について調べてみます。
リンギングの原因について
リンギングの原因について
リンギングは寄生インダクタンスと寄生容量が共振することによって発生します。
では、寄生インダクタンスと寄生容量はどこで発生しているのでしょうか。
ここでは大まかな発生原因について記載いたします。
寄生インダクタンスについて
電流が生じると、それに合わせて磁場が発生します。
このことによりパターンがインダクタの役割を持ってしまいます。
これが寄生インダクタンスの正体です。
パターンが長くなればそれだけ寄生インダクタンスは増えることになります。
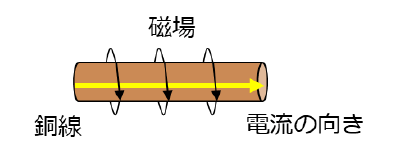
寄生容量について
寄生容量はパターンとパターンの間などに生じます。
スイッチング電源の場合、IC内部のFETに寄生容量が含まれます。
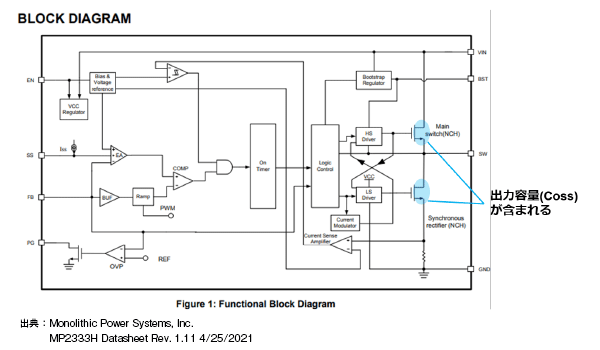
MP2333Hの特長
MP2333Hは、同期整流型降圧型コンバーターで、下記のメリットがあります。
- 動作形式がCOT動作となっているので、負荷変動に対する応答性に優れています。
- 過電流保護機能、低電圧保護、サーマルシャットダウンといった、デバイスを保護する機能が備わっています。
- ソフトスタート機能をユーザーが設定することが可能です。
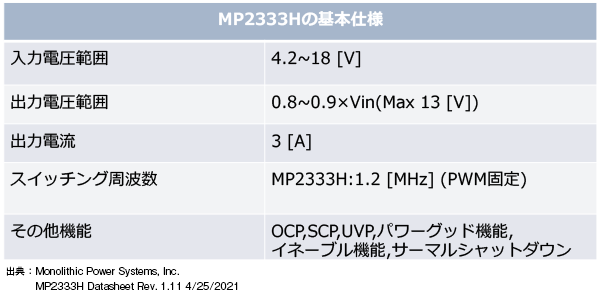
すぐに評価を始められる評価ボード
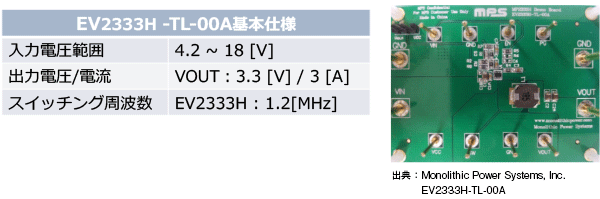
測定内容について
どうすればリンギングノイズを削減できるのか調べるために EV2333H-TL-00A を参考に 2層と4層の2種類の基板を作成しました。
測定項目
- リンギングノイズ
EV2333H-TL-00Aの回路図は以下の通りです。
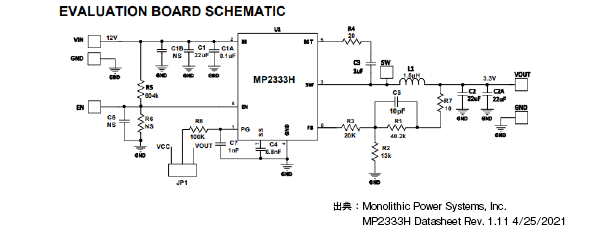
オリジナルレイアウト①について
EV2333H-TL-00Aをもとに作成した2層基板です。
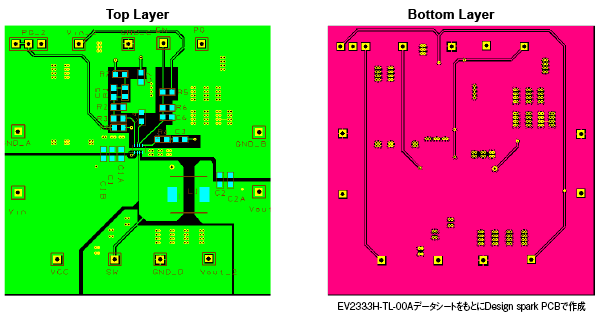
オリジナルレイアウト②について
EV2333H-TL-00Aをもとに作成した4層基板です。
2層目にベタグランドを追加しています。
3層目は未使用です。
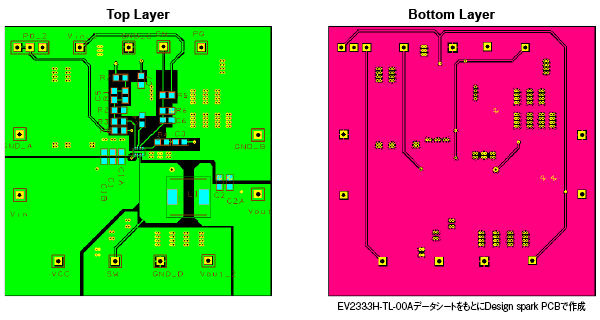
測定環境
以下の測定環境で評価を行います。
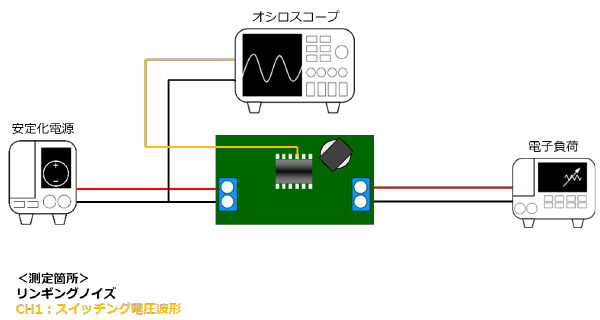
実際の測定の様子
SWノードにリンギング測定用のビアを設けています。
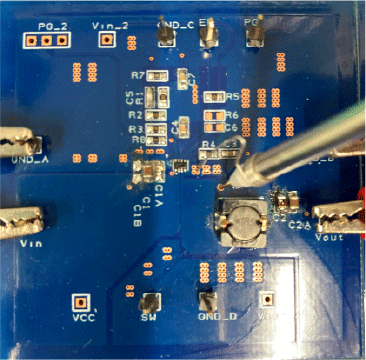
オリジナルレイアウト①の測定結果
出力電流を3Aで設定している時の通常動作時の波形です。
12V入力に対して最大で19.3Vのリンギングが発生しています。
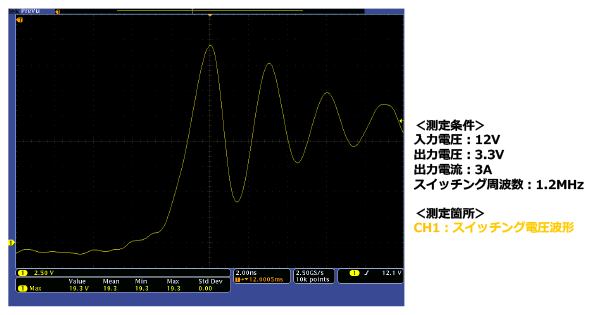
オリジナルレイアウト②の測定結果
出力電流を3Aで設定している時の通常動作時の波形です。
12V入力に対して最大で14.4Vのリンギングが発生しています。
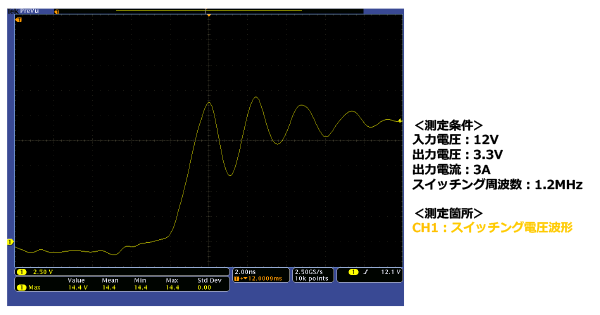
評価結果
グランド層を増やすことで、19.3Vから14.4Vとリンギングを削減することができました。
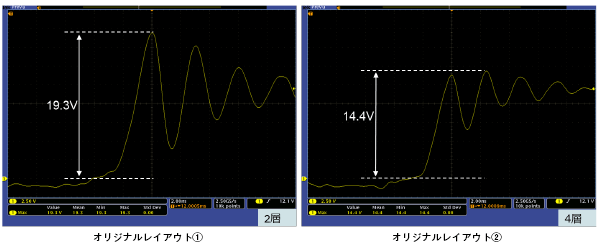
まとめ
下記に結果をまとめた表を記載します。
結果からグランド層数を増やすことでリンギングのピーク値をおさえることが確認できました。
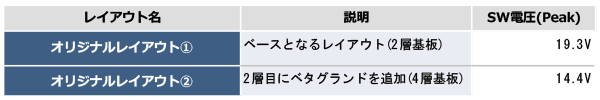
担当エンジニアからの一言
今回2層基板では定格ギリギリまでリンギングノイズが出ていましたが、ベタグランドの追加によって、入力電圧に対して約41%低減することになり、SWピンの絶対最大定格に対して余裕をもつことができました。
このことから、適切なレイアウトを作成する重要性が身に染みてわかりました。
電源基板を作成する際にベタグランドの追加が推奨されていることが多いですが、実際に効果を確かめることができました。
しかし、リンギングの発生原因に対して直接対処できているわけではないので、次回は寄生インダクタンスを小さくする対策をしてみます。