現場で役立つ 発振回路のトラブル回避手法
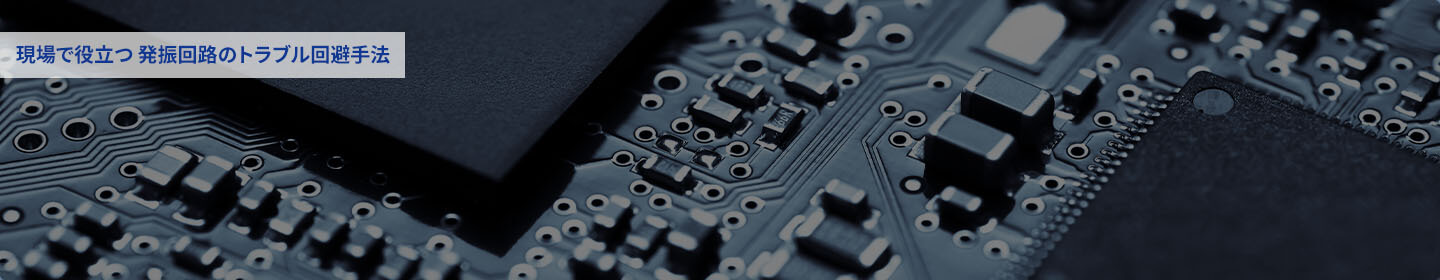
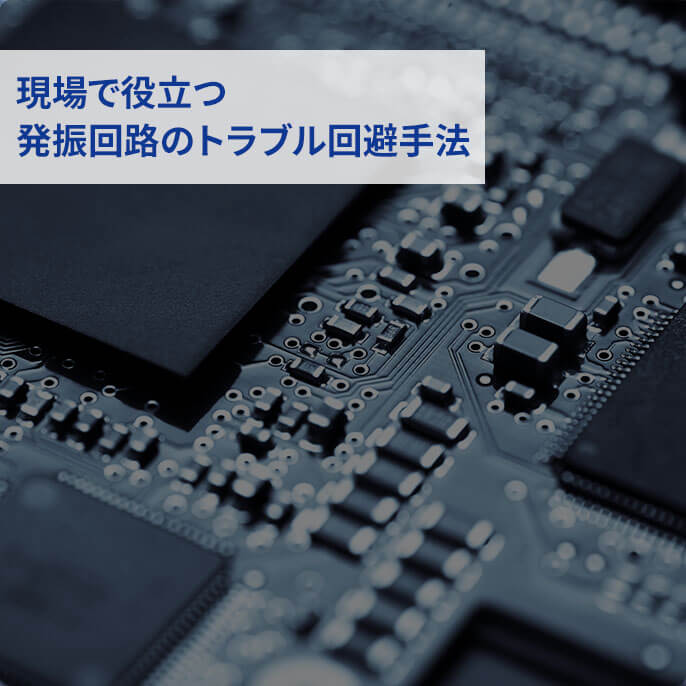
トラブルが発生したら
多くのICで用いられている「発振子を用いた発振回路」。
発振トラブルは評価が出来ずに開発がSTOPしてしまう重大なトラブルです。そのようなトラブルには発振回路に対する認識不足や誤解から生まれていることが多く、とても苦労された方も多いと思います。そんな状況になったら、まずは落ち着いて次のことを確認してみてください。
発振回路のトラブルとは
量産基板の評価開始直後に・・・
- 基板に電源をいれたら全く動かない。
- デバッガがつながらない。
- 電源電圧はチェックし正常だが、なにも動かない。
トラブルが発生した瞬間は「えっ、そんなはずはない」「ちゃんと見直しもしたし、正しく動くはず。なんでなんで・・・どこにバグ(問題)あったの?」っと、あせってしまい頭が真っ白になってしまいます。
ようやく「あっ、CLOCK出力が出ていない! 発振回路が動いていない!」
違う基板を次から次へと調べてみても、どれもこれも発振していません。評価ボードでは動いていた発振回路が試作基板では動いていないのです!
みなさんならこんな時どうしますか? まずは上司、チームリーダに報告?
トラブル発生
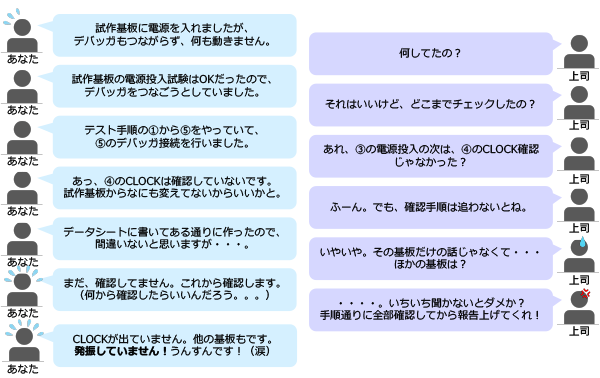
まずは落ち着く、次に確認する
さてこのやり取りの中に、「発振回路でのトラブル」特有の認識不足と誤解がありましたが、皆さんはわかりましたでしょうか?
特にデジタル回路をご専門にされている方が、陥りやすい誤解として、下記があげられます。
- 発振回路はアナログ回路である。
- アナログ回路は、回路図通りの部品・回路定数でも基板が変わると動かない場合がある。
- アナログ回路は、特性に幅を持つので(機能評価だけでなく)特性評価が必要。
先ほどの例では、「新規設計の基板では動かない可能性がある」ということに気づいていなかったことがわかります。ちょっとした認識不足が原因かも知れませんが、期日の決まった基板の立ち上げ時に、想定外の手戻りが発生した時の青ざめる気持ちは、昔も今も変わらないことだと思います。
このようなことにならないように、はじめて基板立ち上げに取り組む新人のために、発振回路を正しく立ち上げる方策について考えていきましょう。
発振回路が発振するための3条件
発振回路が発振するためには、下記の3つの要素が必要です。
- IC(発振入出力端子)・・・Unbufferedな発振回路用のinverterです。
- 基板(パターン)・・・寄生容量などの寄生成分はできるだけ小さいほうがいいですが、場合によってはなかなか思い通りにはならないものです。
- 発振子と外部素子(抵抗とコンデンサ)
この3つの要素の一つが変わっても、デリケートな発振回路は正常に発振しなくなります。
今回の事例で「発振しない」トラブルとなった原因は、新規に基板を設計することで、基板が変わり、基板パターンが変わり、パターンの寄生容量と寄生抵抗が変わることによって、デリケートなバランスが崩れてしまったことだと考えられます。
さて、今回の事例のようなことにならないためには、どのように考えていけば良いでしょうか?
実際はどうする
では、原因が見えてきたところで実際の検討ですが、先に示した3要素を考えるとそれぞれ下記の制約があります。
発振回路3要素の制約条件
- ICの特性は(個別に)変えられない。・・・①
- 基板の特性(寄生容量・寄生抵抗)はパターンを作らないとわからない。・・・②
- 発振子と周辺素子(抵抗・コンデンサ)は変更可能。・・・③
というように、変更・調整可能なのは③の発振子と周辺素子だけとなります。
ですので、発振回路を決める際は、「IC:①」を載せた「基板:②」を用意してマッチングの取れる「発振子と周辺定数:③」を決めていきます。(変えられないものを決定してからマッチングを行う)
このノウハウは発振子メーカが得意としているので、発振子の採用を前提にご相談されることが一般的であり、近道です。
また、発振子メーカのWebページには、IC型番からマッチングの取れる発振子と周辺定数の情報を入手できる検索サイトもありますので、そちらも有効な情報です。
もう一つ知っておきたいこと
ここまでは、発振回路に対する取り組み方を説明してきました。
ここではちょっと細かい内容になりますが、初心者がよく失敗しがちなことをご紹介します。
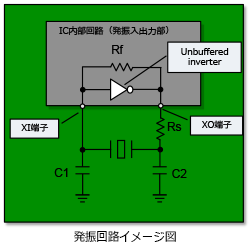
1.発振回路の測定でのよくある失敗
・XI端子にプローブを当ててしまい、最悪発振が止まってしまう。
測定はXO端子にて行う(XIの端子は安易にプロービングしてはいけない)
⇒XI端子はRfの抵抗でDCバイアスされただけの入力端子なので、大変インピーダンスが高くなっています。安易にオシロのプローブ(通常対地10MΩ程度)で触れてしまうと、振幅や周波数への影響、または発振停止など本来の動作では無くなってしまうことを知っておいてください。
・発振回路の正確な周波数測定では、プローブを接触させません。
⇒プローブの入力容量により周波数に影響が出る場合があります。
2.その他キーワード(発振子・発振回路)(ご興味がありましたら、ぜひ調べて見てください)
・負性抵抗、発振余裕度
・Overtone:Fundamental、3rd overtone(X’tal)
担当エンジニアからの一言
今回は意外と知っているようで知らずに使っていて、時々基板設計者がトラブルに陥る、発振回路の落とし穴について紹介しました。
細かい技術的なポイントは省きましたが、今回の最低限の知識だけでも知っておくだけで、青ざめるような事態からは回避できるチャンスは得られるかと思います。
皆さんが困ったことに陥る前に知っておいた方が良い知識として、ちょこっと読んで心に留めて置いて、何かの際の気づきとして少しでも皆さんのお役に立てればうれしく思います。

