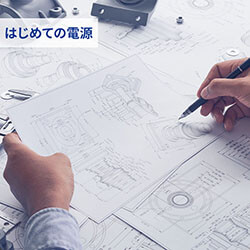現場で役立つ 電源回路の設計方法
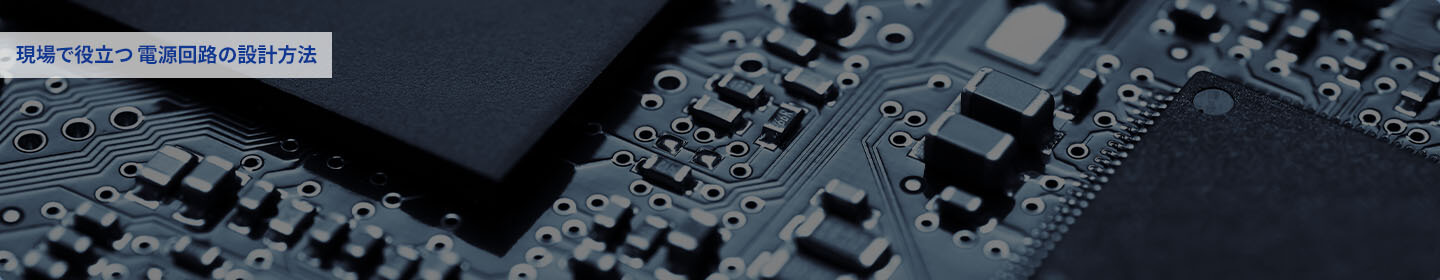
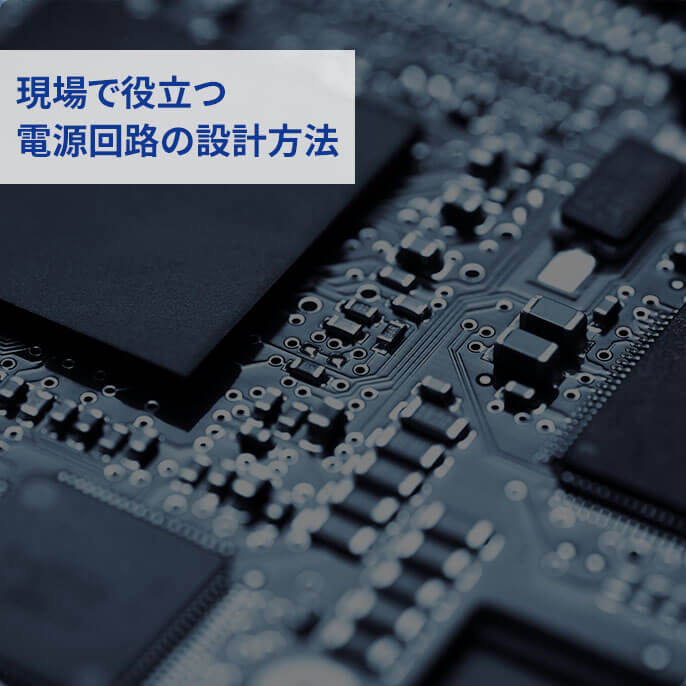
電源回路の設計への不安
実際に定数を選定していく際にこのようことを思ったことはないでしょうか?
・電源の知識や経験がないので定数なんて決められるか不安・・・
・問題が起きにくい定数を選ぶにはどうすればいいんだろう?
・時間もないし最低限見るべきポイントってないのかな?
今回は、そのような疑問やお悩みの解消に協力するべく、一般的なDCDCスイッチングレギュレータの1つであるMonolithic Power Systems社(以下、MPS社と表記)のMP2333Hを用いて、そんなに難しくない回路定数の選定方法を説明します。
回路定数選定とは?
回路図作成時に必要な設計
回路定数選定とは、仕様に合わせて採用したデバイスの周辺部品定数を選定することです。
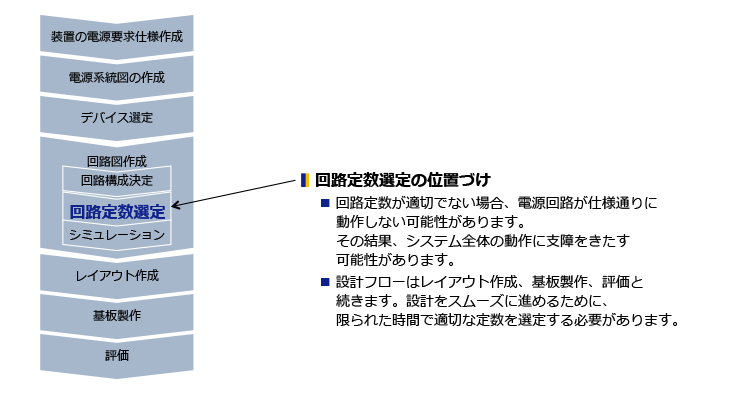
回路定数の選定フロー
●今回は回路定数選定について、下記①~⑤のフローに沿って説明していきます
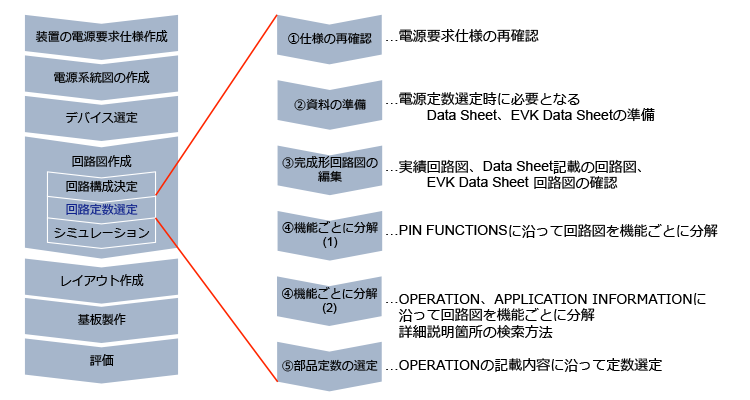
①仕様の再確認
●デバイス選定時に決定した仕様の再確認
・電源回路定数は要求仕様を満たす定数を選定する必要がありますので、要求仕様を表にして確認します。
・要求仕様を表にまとめただけですが、定数の設定ミスを防ぐために非常に重要な表です。
●要求仕様表記載の例
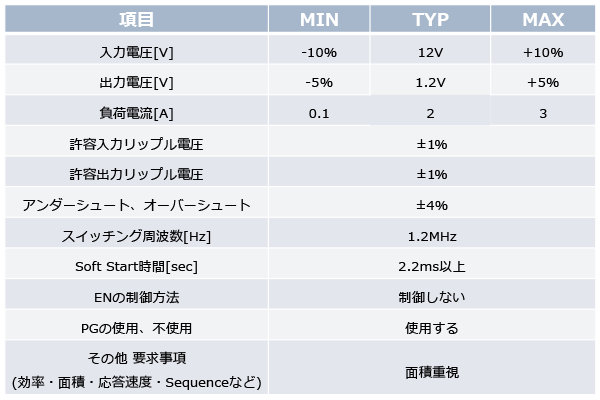
②資料の準備
●回路定数選定を行うために、2つの資料を用意します。
・最新の英語版Data Sheet
・使用デバイスのEVK(EValuation Kit)の Data Sheet
各資料のポイントと特長について詳しく説明します。
最新の英語版Data Sheet
●定数選定に必須の資料
・Data Sheetには電源ICの詳細な説明や、機能の説明が記載されています。
また、定数選定に必要な計算式や推奨値も記載されています。
・確認する際には、WEBに公開されている最新版のData Sheetを用意してください。
●Data Sheetで確認すべき項目
・Data Sheetの内容はすべて重要ですが、回路定数選定の際に特に確認するべき項目は下記4つです。
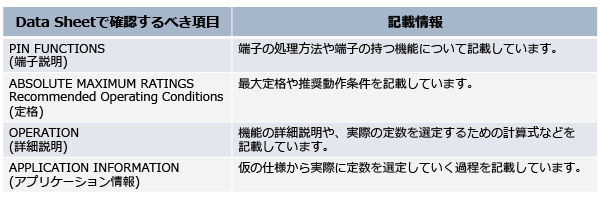
EVKのData Sheet
MPS社製DCDCスイッチングレギュレータは、ほとんどのデバイスでEVKを用意しています。
EVKのData SheetはWEBサイトから閲覧、ダウンロード可能です。
●回路定数情報が満載
・EVKのData Sheetは、動作チェックされた回路図やレイアウトが記載されています。
・回路定数選定の際には、設計者側で任意に決定しなければいけない条件があります。
その際には、EVKの値を参考にすることで、スムーズに定数選定ができます。
●EVKのData Sheetで活用できる項目
・EVKのData Sheetには、定数選定に利用できる下記項目があります。
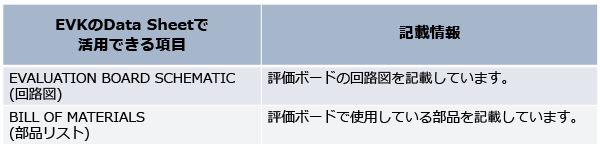
●有用ではあるが、あくまで参考情報
・EVKのData Sheetの回路定数は動作チェックされた定数のため、非常に有効な情報です。しかし、あくまで参考情報であり、お客様が設計する基板で必ず動作することを保証した値ではありません。定数の妥当性については、お客様での評価にて判断してください。
③完成形回路図の編集
完成している回路図の定数を編集
何もない状態から定数選定を行うと時間もかかり、多くの知識や経験が必要です。
そこで最も簡単な方法は、すでに完成されている回路図を用意し、完成形回路図の定数を編集していく方法です。
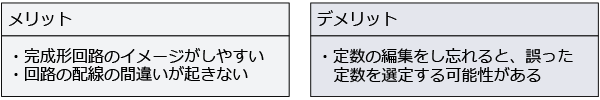
参考にできる回路の特長を考慮し、編集する完成形回路を決定
新規採用のデバイスの場合はData Sheetの“TYPICAL APPLICATION”やEVK Data Sheetに記載のある回路を参考にできます。それぞれの回路にはメリット・デメリットがありますので、用途に合わせて選択してください。
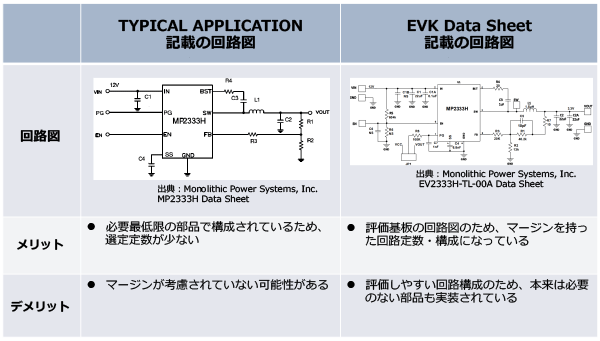
④機能ごとに分解(1)
定数選定前に必ず行うべき項目
今回は“TYPICAL APPLICATION”の回路図を完成形回路図として用意し、周辺部品を機能ごとに分解します。この作業により簡単な回路も複雑な回路も、同じように電源回路定数を選定できます。
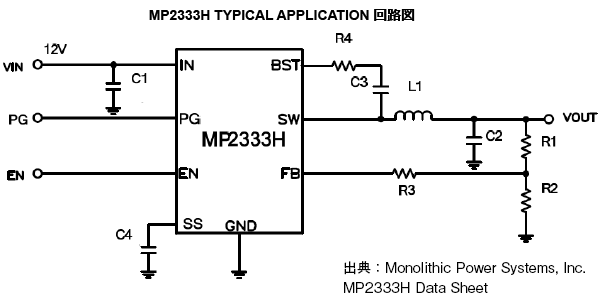
Pin Functionsの活用
“PIN FUNCTIONS”は端子の説明だけでなく、その端子の持つ機能や、端子処理の方法などを記載しています。“PIN FUNCTIONS”の説明内容を用いれば、ある程度、完成形回路図の定数を機能ごとに分解できます。
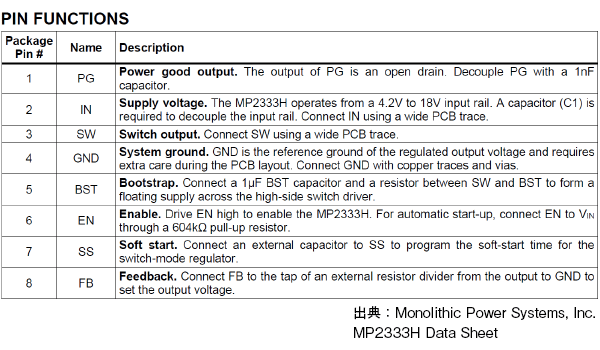
さっそくMP2333Hの回路図を例に機能ごとに分解します。
まずは [SS端子] を例に定数選定を行います。
“PIN FUNCTIONS” に記載されているSS端子の説明内容を確認
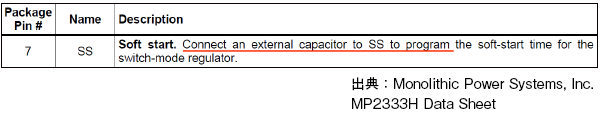
赤線部には、外部にコンデンサを接続すればSS(Soft start)時間をプログラムできると記載されています。この説明文より、SS端子はコンデンサを実装して使用することが確認できます。
PIN FUNCTIONSの内容通りに、端子と回路定数を分解
完成回路図のSS端子の周辺を確認すると、SS端子にはC4のコンデンサが接続されています。“PIN FUNCTIONS”で記載されていたコンデンサがC4だとわかりましたので、SS端子とC4を一つにまとめます。
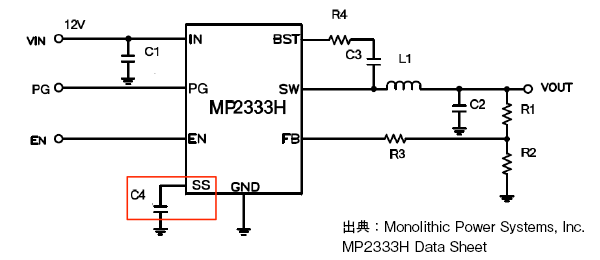
完成回路図からC4とSS端子を分解できました。
同じように、“PIN FUNCTIONS”の表を利用して、端子と回路定数を分解します。
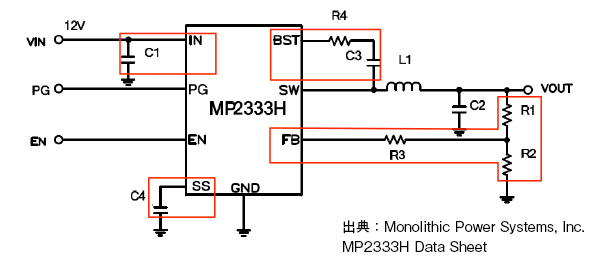
“PIN FUNCTIONS”の記載内容で上記のように分解できました。
④機能ごとに分解(2)
“OPERATION” や “APPLICATION INFORMATION” の活用
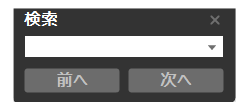
“PIN FUNCTIONS”に記載のない回路定数は詳細説明を確認することで、機能ごとに分解できます。詳細説明は“OPERATION”や“APPLICATION INFORMATION”に記載されています。Data Sheetを順に読んでいくと記載部分を探し出せますが、検索機能を活用すれば、より簡単に該当部分を見つけることができます。
部品名で検索
残った回路部品がどのような機能を持っているのかわからない場合には、部品名で検索をします。今回はL1の詳細説明項目を確認するために、L1を示す [Inductor] をキーワードとして、検索をします。
検索すると、“APPLICATION INFORMATION”にInductorについて、詳細に説明をしている項目が見つかりました。
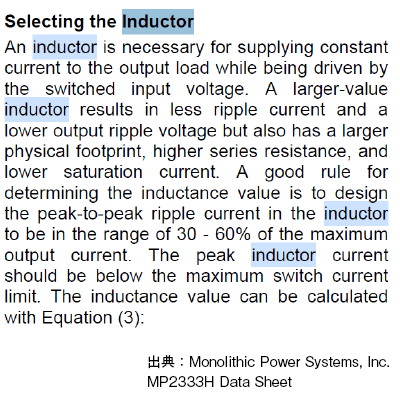
この記載には、L1のインダクタンスをどのように決定すればよいのかが記載されています。
Inductor単体で定数を決定するため、回路図を分解します。
“PIN FUNCTIONS”や“OPERATION”、“APPLICATION INFORMATION”を活用し、完成回路図を機能ごとに分解した回路図が下図です。
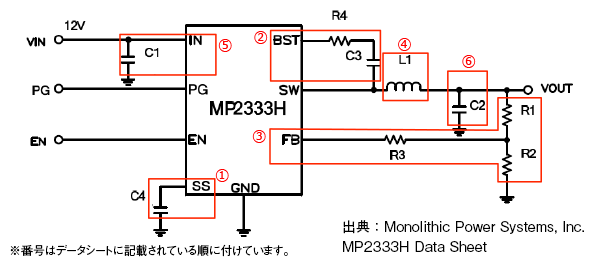
最後に、機能ごとに分解した各回路定数を仕様に合わせて選定します。
⑤電源回路定数の選定
“OPERATION” や “APPLICATION INFORMATION” の詳細説明通りに定数を選定
機能の詳細説明には、推奨される定数や定数選定のための計算式が記載されています。
先程と同じように、検索機能を活用してSS端子の詳細説明を確認し、C4の容量値を選定します。今回は“PIN FUNCTIONS”に記載されていた[soft start]で検索します。
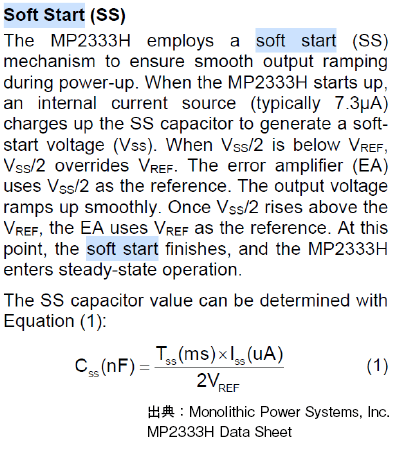
検索をすると、”Soft Start (SS)“という項目で、機能の説明と必要なコンデンサの値を求める計算式が記載されていました。
今回は仕様表の例に従って、Soft Start時間が2.2ms以上となる容量値を求めます。
“OPERATION”に記載されている計算式の[Tss]に2.2msを代入して計算します。また、計算式の[Iss]及び[Vref]は電気的特性に記載されている、Typの値を使用します。
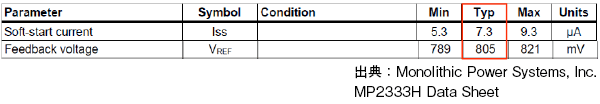
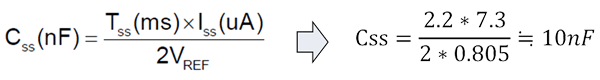
計算結果は約10nFとなりました。
完成形回路図の定数を編集
最後に、先程求めたコンデンサの容量に値を編集します。
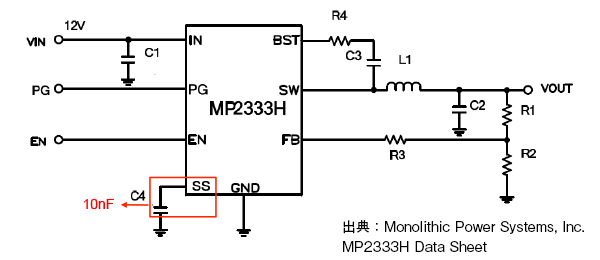
これでSS端子に実装するコンデンサ容量が選定できました。
担当エンジニアからの一言
今回説明したフローは、すでに決まっている仕様や、WEBからダウンロードした資料の情報で回路定数選定を行うためのフローです。この進め方を理解するだけでも、ある程度の定数を選定できます。
しかし、今回選定した定数が本当に正しいのかどうかについては、最後の“評価”によって判断する必要がありますが、このフローが少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。