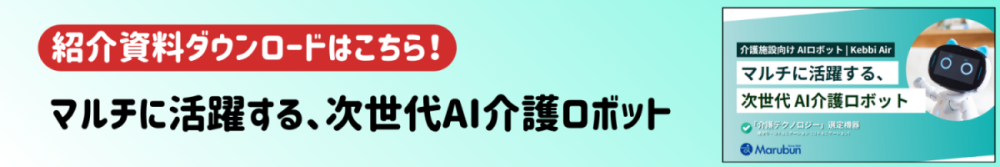介護施設でおすすめのレクリエーションは?実施するメリットについても解説
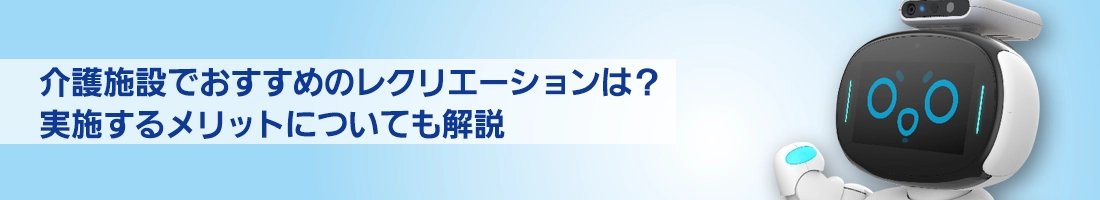
介護施設においては、レクリエーション活動を積極的に取り入れることが推奨されています。
この記事では、高齢者向けレクリエーションの種類や具体的な内容などについて解説します。高齢者向けのレクリエーションについて詳しく知りたい人や普段行っているレクリエーション以外にも興味がある人は、参考にしてください。
AIコミュニケーションロボット Kebbi Air(ケビー・エアー)概要紹介はこちら
お問い合わせはこちら
レクリエーションを行うメリット
レクリエーションを行うメリットについて解説します。
生活の質(QOL)が向上する
高齢者はレクリエーションを楽しむことで、日常生活に楽しみが生まれ、心の満足感が得られます。これらの活動が「生きがい」として日々の楽しみになることもあり、新しい趣味や興味を見つけることで、毎日の生活に目的や目標が生まれ、充実感が増し生活の質(QOL)が向上します。
心身が健康になる
レクリエーションを行うメリットは、心身が健康になることです。レクリエーションを通して、楽しみながら体を動かすことは健康維持に役立ちます。適度な運動は身体を健やかに保つだけでなく、気分転換にもつながります。
レクリエーションを実施する際の流れ
ここからは、レクリエーションを実施する際の流れについて具体的に解説します。
あいさつ
参加者がそろったら、最初にあいさつを行います。スタッフが笑顔で元気に声をかけることで、参加者の緊張が和らぎ、明るい雰囲気で始められます。
説明
あいさつの後には、行うレクリエーションの内容をわかりやすく説明します。参加者が内容をしっかり理解できるよう、ゆっくりと説明し具体的な手順を伝えましょう。
少し複雑な内容の場合には、実演を交えるのがおすすめです。実際にスタッフが動きを見せることで、言葉だけでは伝わりにくいポイントを理解してもらえます。
実施
内容の説明が終わったら、実施に移ります。進行中には参加者の様子を確認し、適宜フォローや声かけを行いながら進めていきます。
終了後には、参加者に感想を聞いてみるのもよいでしょう。楽しんでもらえた点や改善が必要な点を教えてもらうことで、次回のレクリエーションに役立てられます。
レクリエーションの種類
ここでは、レクリエーションの種類について解説します。
身体を動かすレクリエーション
代表的なレクリエーションの1つとして、身体を動かすレクリエーションが挙げられます。
身体を動かすレクリエーションはさまざまな種類がありますが、軽い運動を通してストレス解消が期待できます。適度に運動をしながら楽しく体を動かせるため、誰でも気軽に参加しやすいのが特徴です。
脳を動かすレクリエーション
クイズやパズルなど脳を刺激するレクリエーションは、認知機能の維持・向上に効果的です。加えて、クイズやパズルで行き詰った際、高齢者に周りとの相談を促しコミュニケーション機会の創出も行えます。
音や歌を用いるレクリエーション
音楽や歌を取り入れれば、高齢者の聴覚を刺激できます。また、リラックスして音楽に触れることで、不安や緊張感を和らげる効果が期待できます。雰囲気を明るくしたい場合や落ち着きたい際におすすめです。
手や指を動かすレクリエーション
手や指を使うレクリエーションは、細かい動作による脳の刺激を通して認知能力の低下を防ぐ効果があります。折り紙や工作、簡単な手芸など、創造的な活動を楽しみながら脳を活性化させられます。
身体を動かすレクリエーションの例
ここでは、身体を動かすレクリエーションについて具体例を紹介します。
体操
身体を動かすレクリエーションの代表例は、体操です。
ラジオ体操やリズム体操は、足腰を鍛える効果や筋力低下を防ぐ効果があります。椅子に座って行う体操もあり、参加者の体力に合わせて調整可能です。椅子に座った状態で行う体操は、立って行うのが難しい方でも安全に参加でき、同様の効果を得ることができます。例えば、椅子に座ったまま足を上げ下げしたり、腕を動かしたりすることで、筋力や柔軟性を鍛えることができます。
風船バレー
風船バレーは、風船を落とさないように手で打つシンプルなゲームです。椅子に座ったまま参加できるため、安全で手軽に楽しめます。得点制にすればより白熱するでしょう。またチーム分けをすることで、他の参加者とのコミュニケーションが促進されます。これにより、孤立感を防ぎ、社会的なつながりを感じることができます。
輪投げ
輪投げは目標に向かって輪を投げ入れるゲームで、指先の力や集中力が必要です。新聞で輪を作り、ペットボトルをピンにすることで簡単に準備ができます。声掛けをしながら盛り上がるよう進行しましょう。
魚釣りゲーム
魚釣りゲームでは、磁石とクリップ付きのおもちゃを使って魚に見立てたアイテムを釣り上げます。制限時間内で多く釣った人が勝ちというルールにすると盛り上がります。また、魚ごとにポイントをつけて、獲得したポイントで勝ち負けを決めるのもよいでしょう。
脳を動かすレクリエーションの例
次に脳を動かすレクリエーションの例について解説します。
間違い探し
間違い探しは似たイラストを比較して違いを見つけるゲームで、集中力や観察力を鍛えます。脳に刺激を与えられるため高齢者におすすめです。制限時間を設定し、見つけた間違いの数を競う形式を取るとよいでしょう。
しりとり
誰でも知っている遊びといえばしりとりです。シンプルなルールでありつつ、季節ごとのお題や世界の有名な観光地などお題を変えるなどの工夫をすることで飽きずに遊べます。
難易度は上がりますが、暗記しりとりや絵しりとりもおすすめです。
漢字読みクイズ
漢字読みクイズは、難しい漢字や珍しい漢字の読み方を答えるゲームです。進め方は、カードやホワイトボードに漢字を書き、順番に答えてもらう形式などをとるとよいでしょう。複数の選択肢を用意し、択一式にすれば、参加者がより答えやすくなります。また、チーム形式にし、チーム内で回答について相談する時間を設けることでコミュニケーションを促すことも可能です。
回文
回文は、前から読んでも後ろから読んでも同じ文章を考える遊びです。回文の代表的な例は「しんぶんし」が挙げられます。回文を1から考えるのは難しいため、穴埋め形式で進行する方法がおすすめです。
音や歌を用いるレクリエーションの例
続いて、音や歌を用いるレクリエーションの例について解説します。
カラオケ
カラオケは高齢者にとって定番のレクリエーションです。懐かしい曲やみんなで歌える歌を選ぶことで、参加者が盛り上がります。また、声を出すことでストレス解消にもつながります。全員が楽しめるよう、誰もが知っている曲を選曲するとよいでしょう。
合唱
合唱は高齢者が無理なく参加できるレクリエーションです。声を合わせて歌うことで一体感や達成感を感じられる点が魅力です。ただし、歌うことが恥ずかしい高齢者もいるため適度なフォローは欠かせません。
輪唱
輪唱は、歌をずらして歌うことを楽しむレクリエーションです。複数のグループが異なるタイミングで歌い始めるため、難易度は高いですが認知機能の維持や向上に効果があります。
手や指を動かすレクリエーションの例
次に、手や指を動かすレクリエーションの例について解説します。
もしもしかめよ
童謡「もしもしかめよ」のリズムで指を折っていくレクリエーションです。指の折り方によって難易度を調整できるため、簡単なレベルをクリアしたら次のレベルに挑戦するなどの工夫ができます。
グーパー体操
グーパー体操とは、グーとパーの動きを繰り返して脳を刺激するレクリエーションです。「グー・パー・グー」のように順番を変えたり、片手ずつ異なる動きを行うと脳が活性化します。
手芸
編み物や手縫いなどの手芸もレクリエーションに向いています。指先を使うため、集中力を高める効果もあります。1人で黙々と作業できるため、他の人とコミュニケーションを取るのが苦手な人でも参加しやすい点が特徴です。
壁画作り
壁画作りは、参加者全員で取り組める集団レクリエーションです。参加者で分担を決め、全員で大きな壁画を作りましょう。壁画は、折り紙や手形などさまざまなバリエーションで作れます。
レクリエーションに必要な準備
ここでは、レクリエーションに必要な準備について解説します。
道具を準備する
レクリエーションで道具を使用する場合、事前に人数分がそろっているか、予備があるかを確認しましょう。また、ホワイトボードなどを使う際には、色や文字の大きさなど、参加者の年齢や身体的な状況に配慮する必要があります。
配置を決める
レクリエーションを円滑に進めるには、参加者とスタッフの配置を事前に確認しましょう。特に、介助が必要な参加者がいる場合は、スタッフを近くに配置し、迅速にサポートできるようにしてください。
また、当日の動きをシミュレーションしておくことも有効です。参加者が移動する際の導線や、スタッフがどのようにお手伝いするのかをあらかじめ想定しておきましょう。
レクリエーションを開催する際の注意点
最後に、レクリエーションを開催する際の注意点について解説します。
無理やり参加させない
レクリエーションを開催する際の注意点は、無理やり参加させないことです。無理に参加を促したり、参加を強要すると、逆にストレスを与えてしまう可能性があります。高齢者それぞれのペースや性格に合わせ、本人の意思を尊重しましょう。
参加者の交流を促す
レクリエーションを開催する際には、参加者同士の交流を促しましょう。レクリエーションは、コミュニケーションの活性化も目的であるためです。
注意点は、参加者全員が自然に交流できるわけではないことです。コミュニケーションが苦手な参加者には、スタッフが適切にフォローを入れることが求められます。