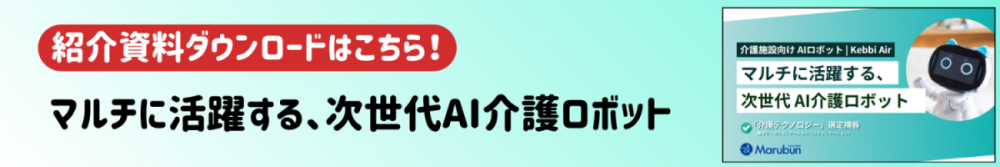介護におけるAIロボットとは?メリットやデメリット、種類など徹底解説
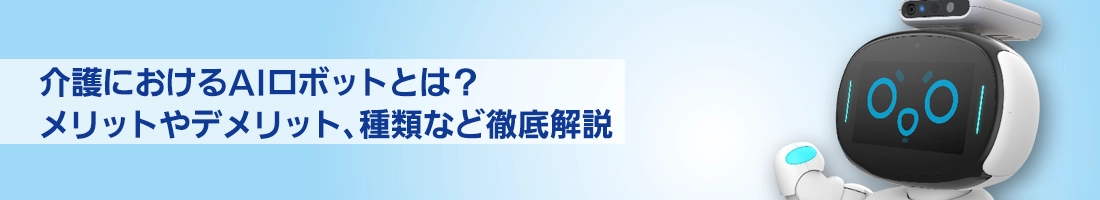
近年、介護機器はIoT技術の進化によりネットワーク化が進み、介護現場で幅広く活用されるようになっています。歩行支援やパワーアシスト機器といったロボット技術に加え、さまざまな介護シーンに対応したAIロボットの開発も進んでいます。
本記事では、介護の現場で注目を集めるAIロボットの役割や特長について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
AIコミュニケーションロボット Kebbi Air(ケビー・エアー)概要紹介はこちら
お問い合わせはこちら
介護業界で活用するAIロボットとは
厚生労働省によると、ロボットとは「情報を感知する(センサー系)」、「判断する(知能・制御系)」、「動作する(駆動系)」という3つの要素技術を備えた、知能化された機械システムと定義されています。
近年、介護機器はIoT技術を活用してネットワーク化され、介護業務の効率化や高齢者の生活支援に役立つシステムとして注目されています。歩行支援やパワーアシスト機器といったロボット技術に加え、高齢者の生活状態をセンシングし、個人に適した支援機器を提案するような新しいサービスも次々と開発されています。
AI(人工知能)とは
AIとは「アーティフィシャル・インテリジェンス」の略で、日本語では「人工知能」を意味します。
AIの導入により期待されるメリットは多岐にわたります。たとえば、生産性の向上や人手不足の解消、人的ミスの低減、さらには膨大なデータを活用した効率的な支援が可能です。介護業界では、これらの特長を活かし、高齢者一人ひとりに適した支援を提供することが目指されています。
介護業界で活用するAIロボットの種類
AIロボットは介護業界で多岐にわたる役割を担い、利用者の生活を支援すると同時に、介護者の負担軽減にも貢献しています。以下では、主に利用されているAIロボットの種類を解説します。
移乗支援
移乗支援ロボットは、ベッドから車椅子、車椅子からトイレといった移乗が必要な場面で活用されています。高齢者や身体が不自由な方を安全に支えることで、介護者が抱える腰痛などの身体的負担を大幅に軽減することが可能です。
また、利用者にとっても、安定したサポートを受けられることで安心感が高まるという利点があります。
移動支援
歩行が難しい方の移動をサポートするための移動支援ロボットも重要な役割を果たしています。AIを搭載した歩行器や電動車椅子は、利用者の動きや周囲の環境を感知し、自動で速度や方向を調整する機能を持っています。
これにより、安全な移動が可能になるだけでなく、利用者の自立を促進する効果も期待されています。
排泄支援
排泄支援ロボットは、利用者の排泄のタイミングを予測し、適切なサポートを行う役割を担います。AIとセンサーを活用して利用者の身体の状態をモニタリングし、排泄の必要がある際に通知を行う仕組みです。
この技術により、利用者の快適さが向上するだけでなく、介護者の負担も大幅に軽減されます。
見守り・コミュニケーション
見守り・コミュニケーションロボットは、利用者の安全を見守りつつ、会話を通じてコミュニケーションを図る機能を持っています。
たとえば、転倒や異常行動を検知して介護者に通知するほか、利用者と会話をすることで認知機能の維持や改善をサポートします。特に認知症の方の見守りにおいては、効果的な活用が期待されています。
入浴支援
入浴支援ロボットは、入浴時の利用者の移動や洗体をサポートするために開発されたものです。安全に体を持ち上げる機能や、洗体の補助を行う機能を備えており、利用者が安心して入浴できる環境を提供します。
このようなロボットは、介護者の身体的負担を大幅に軽減し、より効率的な介護が可能になる点で注目されています。
介護業務支援
介護業務全般をサポートするAI技術を活用したシステムも、介護現場で広く利用されています。たとえば、介護記録を自動で作成する機能や、業務スケジュールを最適化する機能を持つシステムは、介護者の事務作業負担を軽減します。
また、収集したデータを分析し、利用者に最適なケアを提供するための支援も行えるため、ケアの質の向上にもつながります。
介護業界が抱える課題とは
日本の介護業界は、高齢化社会の進展とともに多くの課題に直面しています。以下で詳しく解説します。
高齢者数が急激に増加している
総務省統計局のデータによれば、2024年9月時点で日本の65歳以上の人口は3625万人と過去最多を記録しており、総人口に占める割合は29.3%に達しています。この傾向は今後も続くとされ、2040年には高齢率が約35%に達すると予測されています。
こうした急激な高齢化により、医療や介護サービスの需要が増加する一方で、労働力不足や財政の圧迫といった課題が懸念されています。
要介護者数も増加している
日本の介護におけるもう一つの大きな課題は、要介護者数の増加です。厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、令和4年5月時点で要介護(要支援)認定者数は691.4万人に上っています。
この増加に伴い、介護職員の需要も高まる一方で、人材不足や介護費用の増加による財政の圧迫が懸念されています。
慢性的な人手不足
介護業界では慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。公益財団法人介護労働安定センターが行った令和4年度の調査によると、介護事業所全体の60%以上が人材不足を感じている状況です。
特に、高齢化が進む日本では介護の需要がますます増加するため、人手不足は業界全体の安定に直結する深刻な問題といえます。
介護業界でAIロボットを活用するメリット
AIロボットの導入は、介護現場において多くのメリットをもたらします。ここでは、AIロボットを活用することで得られる主なメリットについて解説します。
作業負担を軽減できる
AIロボットは、移乗や移動支援、排泄補助など、介護者にとって身体的負担の大きい作業をサポートします。これにより、介護者の腰痛や疲労を防ぎ、長期間にわたって介護業務を続けやすくなります。
また、事務作業を自動化するロボットの活用により、業務全体の効率化も図ることができます。
きめ細やかなサービスを提供しやすくなる
AIロボットは、利用者一人ひとりの状態やニーズに応じたサービスを提供するための強力なサポート役です。
たとえば、排泄や入浴のタイミングを個別に通知したり、見守りロボットが利用者の行動や状態を記録・分析したりすることが可能です。これにより、利用者に寄り添ったきめ細やかなケアが実現します。
誰でもスピード感を持って対応できる
多くのAIロボットは、利用者の状況をリアルタイムで把握し、必要な情報を即座に介護者に伝えることができます。そのため、経験の少ないスタッフでも迅速かつ適切に対応することが可能です。
特に緊急時には、迅速な判断をサポートする役割が大きく、現場全体の対応力を向上させます。
健康状態の変化や異常を早期にキャッチできる
センサーやデータ分析機能を備えたAIロボットは、利用者の体調や行動の異変を早期に検知します。たとえば、転倒や心拍数の異常、認知症の兆候などを事前に把握できるため、重大なトラブルを未然に防ぐことができます。
高齢者の孤独感を軽減する
見守りやコミュニケーションロボットは、高齢者と会話をしたり、レクリエーションやリハビリの相手をしたりすることで孤独感を軽減します。
特に、高齢者にとってはロボットが話し相手になることで精神的な安心感を得られ、認知機能の維持にも役立ちます。
介護業界でAIロボットを活用するデメリット
AIロボットは介護業界に多くのメリットをもたらしますが、その導入や運用にはいくつかの課題も存在します。ここでは、主なデメリットについて解説します。
導入コストがかかる
AIロボットを導入する際、初期費用が高額である点は大きな課題です。特に中小規模の介護施設や在宅介護の現場では、導入コストが財政的な負担となる場合があります。
また、導入後も定期的なメンテナンスやソフトウェアの更新費用が発生するため、継続的なコスト管理が必要です。
使いこなせない可能性がある
AIロボットを現場で効果的に活用するためには、介護職員が新しい技術に対する学習や研修を受ける必要があります。
しかし、介護現場の多忙さゆえに十分な研修時間が確保できない場合、ロボットの操作方法や機能を習得しきれず、十分に活用されないまま現場の負担が増えてしまう可能性もあります。
設置場所や保管場所がない恐れがある
多くの介護施設は限られたスペースで運営されており、大型のAIロボットを設置する場所や未使用時の保管場所を確保することが難しい場合があります。
また、施設内の動線を妨げないように設置場所を工夫する必要もあり、スペースの有効活用が課題となることがあります。
まとめ
AIロボットは、介護現場での負担軽減や利用者の生活の質向上に大きな可能性を秘めています。
移動支援や見守り、排泄支援など多岐にわたる業務をサポートするだけでなく、個別ケアの実現や緊急対応能力の向上にも役立つツールです。一方で、導入コストや運用課題、スペース確保といった現実的なデメリットも考慮する必要があります。
AIコミュニケーションロボット「Kebbi Air」は、AI(人工知能)を活用した自然な会話機能に加え、エンターテインメントコンテンツの提供やビデオ通話による見守り機能を備えています。また、体表面温度の測定や受付・入退館管理など、多彩な機能を搭載しており、介護施設やオフィスをはじめ、さまざまな場面で活用されています。