介護ロボットの種類は?9分野16項目の内容やメリット・デメリットを詳しく解説
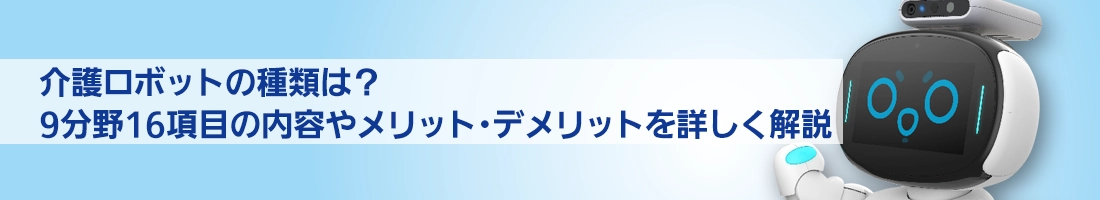
介護ロボットは、大きく分けて3つの種類があり、物理的なサポートだけでなく、精神的なケアを提供するものまで、さまざまなタイプが存在します。
本記事では、介護ロボットの種類について、それぞれの特徴や役割を詳しく解説します。介護ロボットがどのように利用者や介護者を支えているのか、その具体例もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
AIコミュニケーションロボット Kebbi Air(ケビー・エアー)概要紹介はこちら
お問い合わせはこちら
介護ロボットの種類
介護ロボットは主に3つの種類に大きく分けられます。以下で解説します。
介護支援型
介護支援型ロボットは、移乗や入浴、排泄といった介護者の身体的・心理的負担を軽減するために活用されます。例えば、移乗支援ロボットは足腰への負担や無理な姿勢を減らし、介護を行う側の身体的な負荷を軽減します。
また、利用者も気兼ねなくサポートを受けられるため、利用者側の心理的な負担を軽減する効果も期待されます。
自立支援型
自立支援型ロボットは、歩行や食事などの日常生活動作をサポートする役割を担います。
膝装着型のロボットや歩行支援機器などを用いることで、要介護者の身体的負担を軽減し、自立した生活を送る自信と心理的安定感を高めます。これにより、要介護者が自分でできることを増やし、生活の質を向上させることを目指します。
見守り・コミュニケーション型
見守りやコミュニケーション型のロボットは、利用者との会話を通じて認知症予防や精神的ケアに役立ちます。歌やダンスといったレクリエーション機能を備えたロボットや、動きを検知して声掛けを行うものもあります。
また、セキュリティ型のロボットは、転倒や徘徊などの異変を検知して介護者に通知するなど、高齢者の安全を見守る役割を果たします。
介護ロボットの普及率
公益財団法人介護労働安定センターが実施した「令和5年度 介護労働実態調査」によると、事業者向けの介護ロボット導入状況では「導入は検討していない」と回答した事業者が半数以上を占めています。
一方で、「日常的に利用している」と回答した事業者はわずか2%台にとどまっており、介護ロボットの導入は依然として十分に進んでいない状況です。
介護ロボットのメリット・デメリット
介護ロボットは介護現場においてさまざまな利点をもたらしますが、一方で導入や運用に課題も存在します。
介護ロボットのメリット
介護ロボットの最も大きなメリットは、介護者の作業負担を軽減できる点です。
移乗や移動支援、排泄の補助など、身体的負担が大きい作業をサポートすることで、介護者の腰痛や疲労を防ぎます。これにより、介護業務を長期間続けやすい環境を実現できます。さらに、事務作業を自動化する機能を持つロボットもあり、業務全体の効率化を図れるのも魅力です。
介護ロボットのデメリット
一方で、介護ロボットの導入には高額な初期コストがかかることが課題です。
特に中小規模の介護施設や在宅介護では、この費用負担が大きくなる傾向があります。また、導入後も定期的なメンテナンスやソフトウェアの更新が必要となり、継続的なコストが発生します。このように、経済的なハードルがデメリットとして挙げられます。
介護ロボットの重点開発分野
介護ロボットは、介護現場の効率化や負担軽減を目指して開発が進められています。
厚生労働省と経済産業省の取り組みでは、2024年時点で新たに3分野が追加され、合計9分野16項目が重点開発分野として示されています。
移乗支援(装着)
移乗支援ロボットは、高齢者や介助を必要とする方のベッドや車いす、トイレへの移動を支援します。
介助者が装着して使用することで移乗介助時の身体的負担を軽減し安全に介助支援を行えます。また、介助者が一人で操作できる設計が特徴です。
移乗支援(非装着)
非装着型の移乗支援機器は、ベッドや車いすなどに設置されており移乗支援をサポートする器具です。多くの機器は据付け工事を必要とせず、介助者一人で利用可能です。
主にパワーアシスト機能を使用することで、ベッドや車いす間の安全な移動をサポートします。
排泄支援(排泄予測・検知)
高齢者の排泄タイミングを予測・検知する装置で、トイレへの誘導や介助をサポートします。
生体情報や温度・湿度の変化を基に排泄を予測することで、利用者の快適で安全な排せつをサポートします。
見守り・コミュニケーション(施設・在宅・コミュニケーション)
見守りとコミュニケーションに特化したロボットは、主に施設や各家庭で活用されています。
見守り機器は、従来のカメラ型の見守り機器に加えて、センサー等で高齢者の様子を検知するものもあります。例えばセンサーをベッド等に取付けることで入眠時の安否確認や夜間の徘徊防止に繋がります。
コミュニケーションロボットはAIを活用した自然な会話を提供や、服薬や予定のリマインダーを設定して利用者が重要なタスクを忘れないようにサポートすることも可能です。
どちらも業務の効率化に貢献が期待されますが、利用者のプライバシーへの配慮は充分な注意が必要です。
入浴支援
入浴支援機器は、高齢者が安全かつ快適に入浴できるようサポートする装置です。
リフトやストレッチャーなどの機能を搭載しており、転倒リスクの減少や介助者の身体的負担軽減に貢献します。また自動乾燥機能等もあり衛生的な入浴環境を提供します。
介護業務支援
介護業務支援機器・システムは、介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、その情報を基に高齢者への介護サービスに活用することを目的とした装置やシステムです。
リスク予測・検知など、介護業務の効率化とサービスの質向上を実現します。
【追加分野】機能訓練支援
年を取ったり、病気や怪我などが原因で低下した身体機能を維持・改善するための機能訓練支援にも、ロボット機器があります。訓練結果から効果測定を行うことで、効果的なリハビリテーション実現への貢献が期待されます。
【追加分野】食事・栄養管理支援
食事・栄養管理支援システムでは、誤嚥検知や栄養管理を通じて高齢者の健康をサポートし、介護業務の質向上と負担軽減を目指します。
クラウドと連携してデータを管理できるシステムもあり、被介護者の安全性向上と業務効率化が期待されます。
【追加分野】認知症生活支援・認知症ケア支援
認知症生活支援・認知症ケア支援は、認知機能が低下した高齢者が自立した日常生活を送れるよう支援し、個別ケアを提供するための装置やシステムです。
高齢者の日常生活の困難さを解消する工夫を備え、利用者が操作しやすい設計など自立性の向上を目指します。
現場で活用されている主な介護ロボット
介護現場では、厚生労働省が推進する技術開発の一環として、さまざまな介護ロボットが導入されています。
厚生労働省の「介護現場で活用されるテクノロジー便覧」にも記載されているように、介護業務の効率化や利用者の快適性向上に寄与するロボットが注目されています。
AIコミュニケーションロボット Kebbi Air(ケビー・エアー)
「Kebbi Air」は、AI(人工知能)を活用したコミュニケーションロボットで、介護現場や施設において幅広く利用されています。スムーズな会話機能に加え、体表面温度の測定や受付・入退館管理などの多彩な機能を備えています。可愛らしいデザインと頼りになる性能は、利用者に親しみやすい相棒のような存在になるでしょう。
特に特徴的なのは、Kebbi Airが持つ感情表現能力です。5つの性格と8種類の感情を組み合わせた40通りの感情表現により、実際に人と対話しているかのような体験を提供します。
まとめ
介護ロボットは、高齢化社会の課題を解決するための重要なツールとして、多くの注目を集めています。
本記事で解説した9分野16項目の内容からも分かるように、介護支援や自立支援、見守り・コミュニケーション支援など、多岐にわたる用途で活躍しています。そのメリットには作業負担の軽減や利用者の快適性向上が挙げられる一方で、導入コストや操作性に関する課題もあります。
ロボットが抱えている課題解決に対する貢献度合いの検証や、導入~運用期間中の十全なサポートを受けられるかどうかは選定の際に非常に重要な項目です。丸文デモルームでは、ロボットの実機デモで機能の確認や、運用の相談、導入中のサポート内容などお尋ねいただけます。