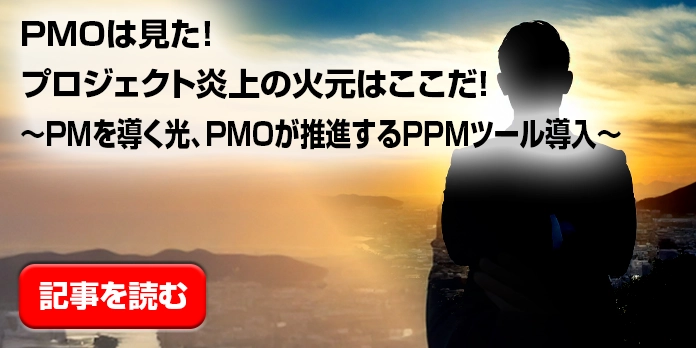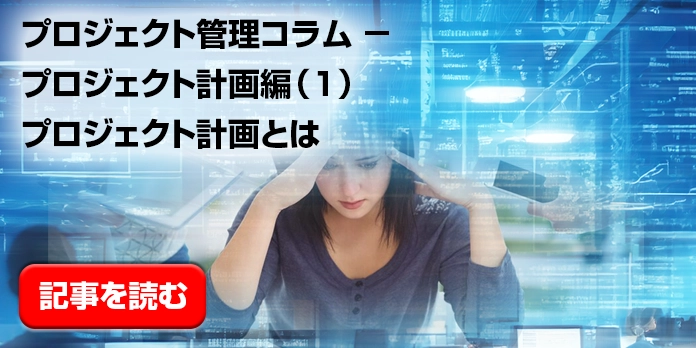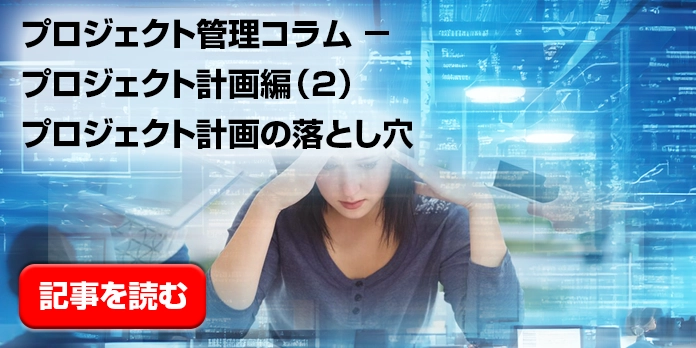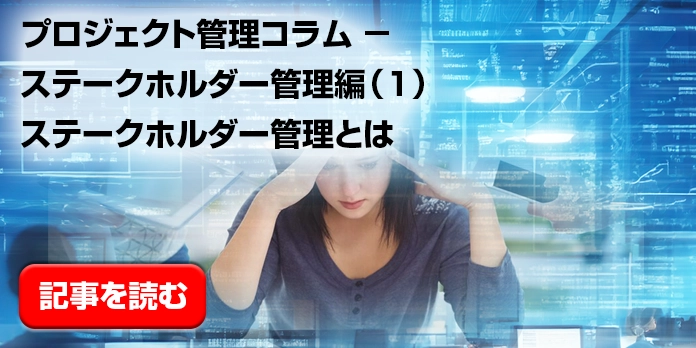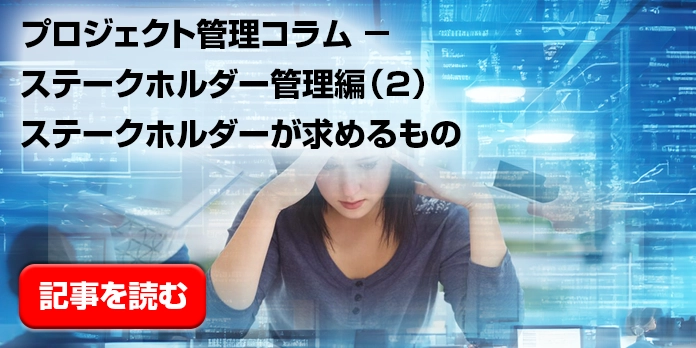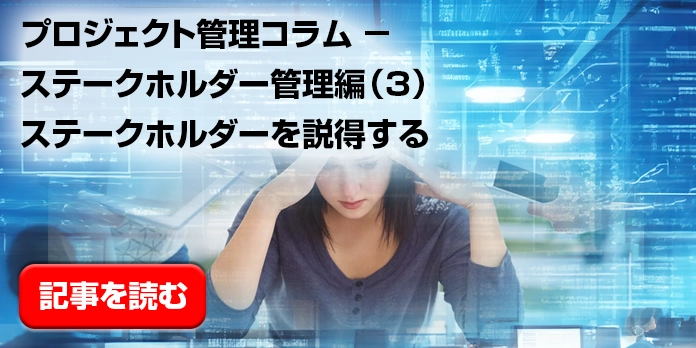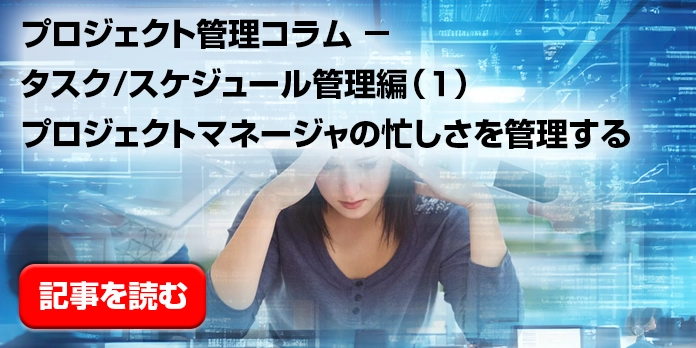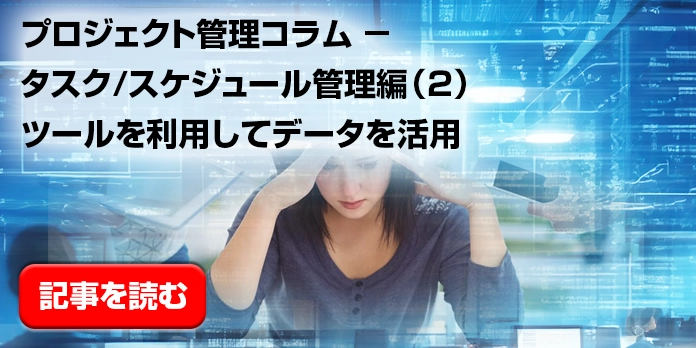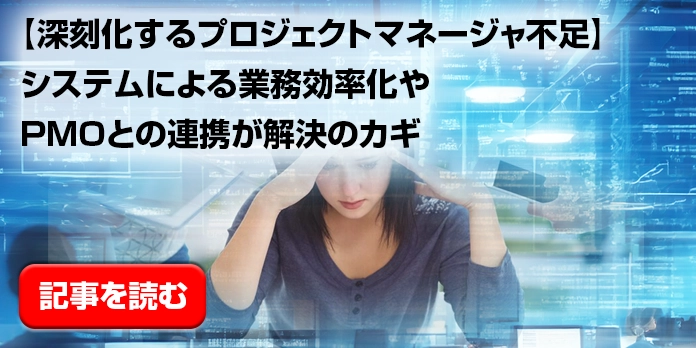PMOは見た!第3回~閉鎖的なコミュニケーションという名の壁~
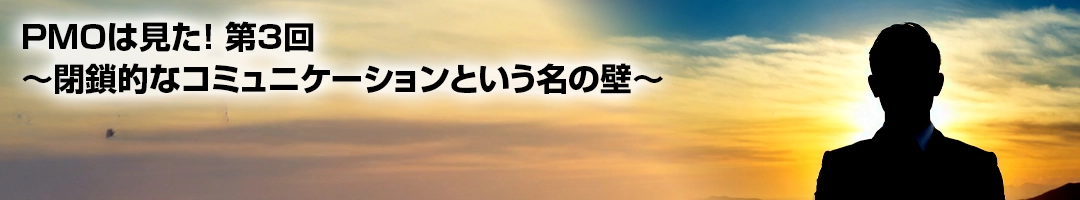
【「孤立するPM」コミュニケーションの壁を打ち破れ!】
「PMOは見た!」第3回は、PMが孤立し、チーム内のコミュニケーションが滞る「火元その2:閉鎖的なコミュニケーションと孤立するPM」に焦点を当てます。中堅PM桧山さんの悩みを例に、情報共有の不足がいかにプロジェクトを危険に晒すかを解説。PMO主導で導入されたPPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)ツールが、どのようにチームの連携を強化し、PMの負担を軽減したのかを具体的にご紹介。PMOによるメンタリングの重要性も詳述します。プロジェクトの課題解決と、PMの孤立防止を目指す方必読です。
登場人物紹介
- 藤崎さん: 主人公。PMO室のエキスパート。プロジェクトの課題解決を支援する。
- 桧山さん: 開発部門の中堅PM。プロジェクトのコミュニケーション課題に直面している。
- 駒田さん: 開発部門の部長。組織全体のプロジェクトマネジメント改善を目指している。
- 加藤さん: 開発部門のベテランPM。桧山さんの指導役も務める。
「藤崎さん、少しお時間いただけますか…?」
開発部門の中堅PM、桧山さんがPMO室の藤崎さんのデスクに、どこか疲れたような表情で立っていた。PPMツールが導入されてまだ日が浅く、社内ではその活用が始まったばかりの時期だった。
「桧山さん、どうぞ。何か困ったことでも?」
藤崎さんが促すと、桧山さんは応接スペースに座り、重い口を開いた。
「実は、担当しているプロジェクトのことで…。最近、どうもチーム内の連携がうまくいかなくて。各自が自分のタスクに集中しすぎて、全体が見えにくくなっている気がするんです。何か問題が起きても、なかなか声が上がってこないというか…」
桧山さんの言葉に、藤崎さんは静かに耳を傾けた。彼のプロジェクトは、新しい顧客向けWebサービスの開発で、技術的に複雑な要素も多い。
「具体的には、どんな状況ですか?」
「例えば、要件定義で合意した内容が、設計担当者と実装担当者の間で十分に共有されておらず、それぞれが異なる解釈で作業を進めてしまったんです。結果、実装フェーズの後半になって初めて、設計意図と完成品に大きなズレがあることが発覚して…。もっと早い段階で認識を合わせていれば、大規模な手戻りは防げたはずなんです」
桧山さんは深くため息をついた。
「チームチャットで共有はしているんですが、流れてしまったり、誰がどこまで理解しているのかが分かりづらくて。僕自身も、個別の進捗確認に追われて、全体像を把握しきれていない感覚があります。駒田部長や加藤さんには相談しているものの、どこまで細かく話すべきか悩んでしまって…」
藤崎さんは、桧山さんの言葉の端々から「孤立感」を感じ取った。これは、PMが1人で抱え込み、チーム全体が閉鎖的になってしまう典型的なパターンだ。PPMツールは導入されたものの、その「使い方」がまだ定着していないがゆえの課題だった。
「なるほど、桧山さん。そのお気持ち、よく分かります。PMが孤立し、チーム内のコミュニケーションが滞ることは、プロジェクト炎上の大きな火元になります。実は、PMOがPPMツールを導入した大きな目的の1つは、まさにその課題を解決することなんです」ここからは、「火元その2:閉鎖的なコミュニケーションと孤立するPM」がプロジェクトをいかに危険に晒すのか、そしてPMOがPPMツールを活用し、いかにこの火元を鎮火できるようになったのかを詳しく解説していきます。
閉鎖的なコミュニケーションという名の壁
プロジェクトは、多様なスキルを持つメンバーが連携し、1つの目標に向かって進む「チーム戦」です。しかし、情報共有が滞り、PMが問題を1人で抱え込んでしまうと、チームはバラバラになり、プロジェクトの成功は困難になります。
この火元が引き起こす問題点:
- 問題の早期発見の遅れ: チーム内で情報が共有されないため、潜在的なリスクや課題が表面化するまで時間がかかり、対応が後手に回ります。
- 手戻りの増加と品質低下: 誤解や認識のずれが原因で、開発途中の手戻りが発生し、結果的に品質の低下や納期遅延を招きます。
- チームの一体感の欠如: メンバー間の連携が不足し、責任の所在が曖昧になることで、チーム全体のモチベーションが低下し、生産性が落ちます。
- PMの孤立と燃え尽き: PMがすべての情報を把握し、単独で意思決定を行うことになるため、過大な負担がかかり、精神的な疲弊や燃え尽き症候群につながることもあります。
PMO主導のPPMツール導入がコミュニケーションの壁を壊す
駒田部長は、過去のプロジェクトでこの「閉鎖的なコミュニケーション」が何度も炎上を引き起こしてきたことを痛感していました。
「昔は、何か問題が起きても、担当者同士で抱え込んでしまったり、PMに報告するまでに時間がかかったりすることが多かった。PMも、忙しさにかまけて、細かな進捗を把握しきれていなかったんだ」と駒田部長は振り返ります。
PMOがPPMツールを導入し、その活用を推進することで、この状況は大きく改善されつつあります。
PMOがPPMツールで実現したこととPMへの支援:
①リアルタイムな情報共有基盤の構築:
・改善前: 情報共有はチャットや口頭が主で、履歴が追いにくく、重要な情報が埋もれがちでした。
・改善後: PPMツールのタスクコメント機能や掲示板機能は、タスクごとの進捗や課題、疑問点をリアルタイムで記録・共有することを可能にします。私たちPMOは、ツールを使った情報共有の習慣化をPMに促し、情報伝達の漏れを減少させます。
②進捗状況の可視化とPMの負担軽減:
・改善前: PMは個別にメンバーに進捗を確認する必要があり、全体の把握に時間がかかっていました。
・改善後: PMツールにメンバー自身がタスクの進捗状況を入力することで、自動生成されるレポート機能を通じて、PMは個別の確認作業から解放されます。私たちPMOは、この機能の活用をPMに促し、PMがより重要な課題解決やリスク管理に集中できるよう支援します。
③PMOによるPMの孤立防止とメンタリング:
・改善前: PMは問題を1人で抱え込み、相談相手が限られていました。
・改善後: 私たちPMOは、PMが抱える課題やリスクをPPMツールで共有し、定期的なミーティングや1on1を通じて共に解決策を検討します。PMOは、PMが安心して相談できる存在として、その心理的な負担を軽減し、適切なアドバイスやサポートを提供します。
④組織横断的なナレッジ共有とベストプラクティスの促進:
・改善前: プロジェクト間の連携が薄く、成功事例や失敗事例が共有されにくい状況でした。
・改善後: PPMツールに蓄積されたプロジェクトデータや課題解決の経緯は、組織全体のナレッジとして活用されます。私たちPMOは、これらのデータを分析し、成功要因や改善点を全PMにフィードバックすることで、組織全体のプロジェクトマネジメント能力向上に貢献します。
数週間後。
藤崎さんと桧山さんは、再びPMO室の応接スペースにいた。桧山さんは以前よりもはるかに明るい表情で、今日の進捗状況を報告していた。
相談後、藤崎さんはPPMツールの活用方法を具体的にレクチャーし、まず桧山さんのチーム内で、全てのタスクとそれに紐づくコミュニケーションをPPMツール上で行うことを徹底するよう促した。これにより、チームメンバーが積極的にPPMツールに書き込むようになり、各自の進捗や抱えている問題がリアルタイムで見えるようになったのが大きかった。
また、週に1度はPMOの定例会とは別に、個別に藤崎さんと進捗や課題をPPMツールを画面共有しながら確認する場を設けた。このメンタリングを通じて、桧山さんは1人で抱え込むことが減り、より安心して課題に立ち向かえるようになった。駒田部長やベテランPMの加藤さんもPPMツールを通じて桧山さんのプロジェクト状況を適宜確認しやすくなり、必要に応じてコメントや具体的なアドバイスを送ることで、タイムリーなサポートが実現していた。
「おかげさまで、以前よりずっとチームの状況が見えるようになりましたし、藤崎さんや加藤さんにも気軽に相談できるようになって、1人で抱え込むことが減りました」
桧山さんの表情には、以前のような疲労の色はなく、明るい兆しが見えていた。
PMOにはプロジェクト内のコミュニケーションの壁を取り払い、PMが孤立することなく、チーム全体でプロジェクトを成功に導くための支援体制を築く役割があります。PPMツールの活用は、その有力な手段となります。次回の「PMOは見た!」では、「火元その3:実現不可能な計画と品質軽視」に迫ります。
【プロジェクト管理に関する情報発信について】
丸文では、効果的なプロジェクト管理に関する実践的な記事やコラムを不定期で掲載しています。記事公開後にメールでの案内を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方は以下のお問い合わせフォームに「Clarityメルマガ配信希望」と記入して送信お願いします。