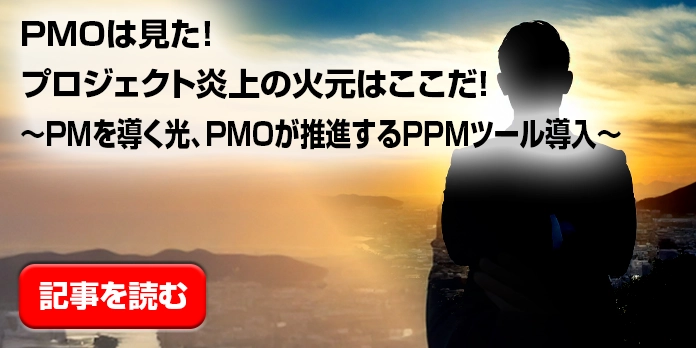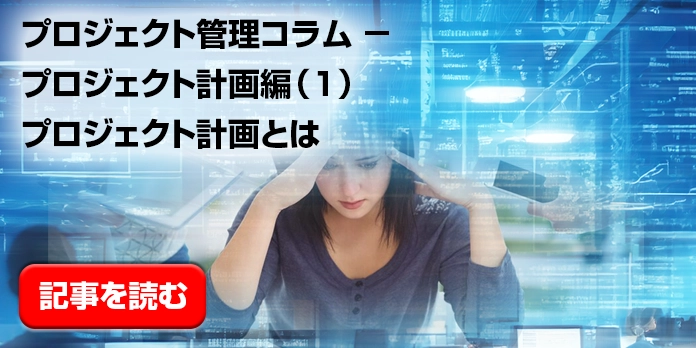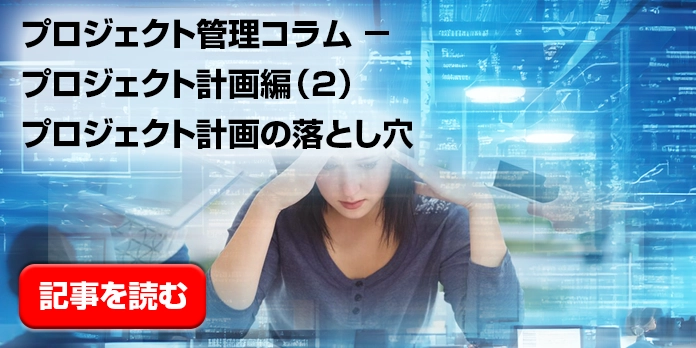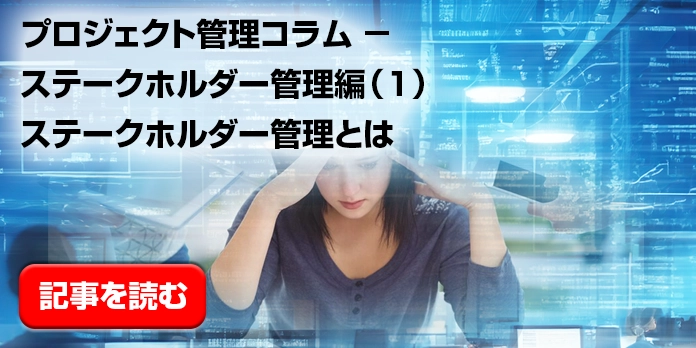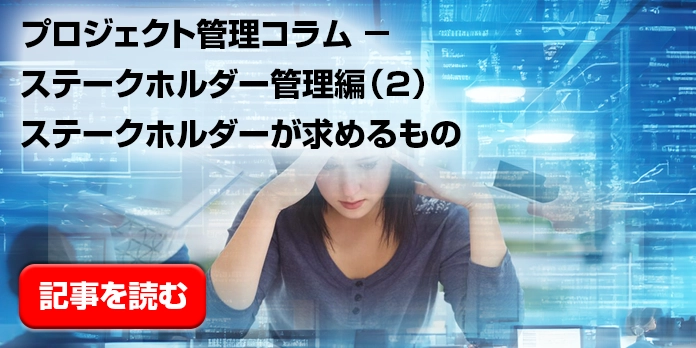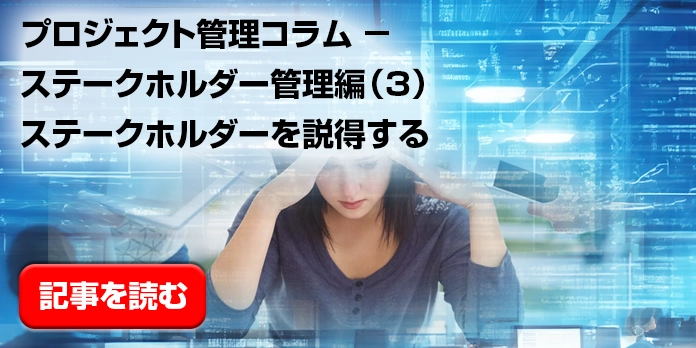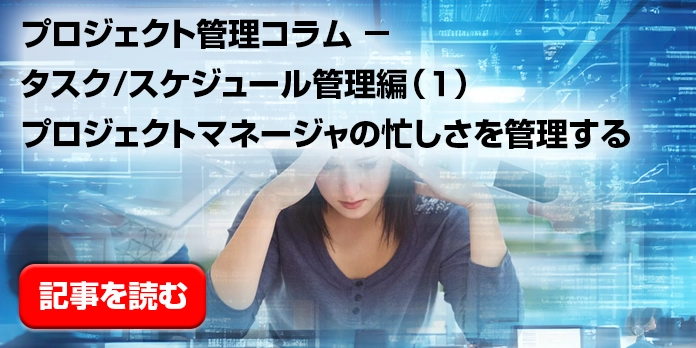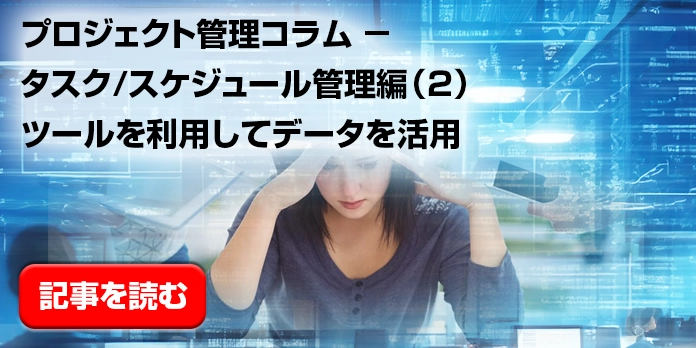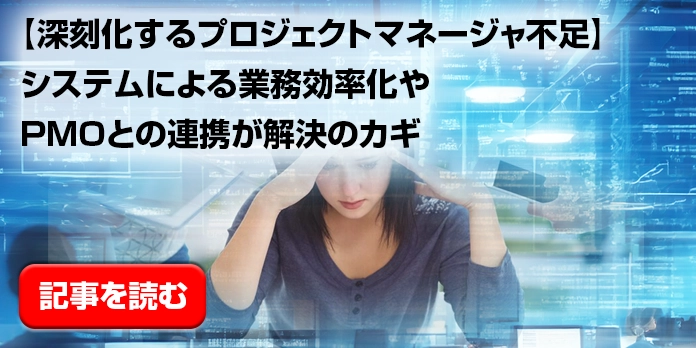PMOは見た!第4回~実現不可能な計画という名の足かせ~
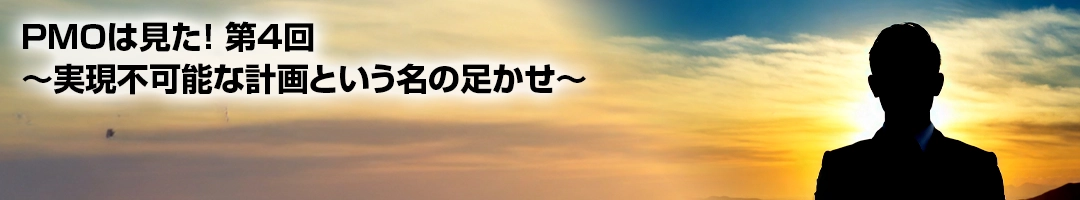
【プロジェクト炎上の火元、完全制圧!無理な計画と品質軽視に終止符を!】
プロジェクト成功を阻む最大の課題の一つ「火元その3:実現不可能な計画と品質軽視」に迫ります。厳しい要求を突きつけられたPM桧山さんが、PMOとPPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)ツールを駆使し、いかに現実的な計画を立て、品質を確保したかを詳述。これまでの連載で触れた要件管理やコミュニケーションの改善も網羅し、3つの火元全てを完全制圧して成功へと導いた軌跡をご紹介します。プロジェクトマネジメントの新たな扉を開きましょう。
登場人物紹介
- 藤崎さん: 主人公。PMO室のエキスパート。プロジェクトの課題解決を支援する。
- 駒田さん: 開発部門の部長。組織全体のプロジェクトマネジメント改善を目指している。
- 桧山さん: 開発部門の中堅PM。PMOとPPMツールの支援で成長。
「藤崎さん、いいタイミングだった。ちょうど桧山君の件で話したいと思っていたんだ」
開発部門の駒田部長が、PMO室の藤崎さんを見つけるなり声をかけた。その表情には、以前のような疲労の色は全くなく、むしろ満足げな笑みが浮かんでいた。
「はい、部長。桧山さんのプロジェクトのことでしょうか?」
藤崎さんが尋ねると、駒田部長は深く頷いた。
「ああ、そうだ。新しいWebサービス開発のプロジェクトだが、あれは本当に素晴らしい。初期の段階でかなり厳しい納期と、盛りだくさんの機能要望があっただろう?正直、また『火元その3:実現不可能な計画と品質軽視』に陥るんじゃないかと心配していたんだ」
駒田部長は椅子に腰掛けながら、感慨深げに語り始めた。
「以前なら、あの手の無理な要求に対して、現場はただ『はい』と答えて、どうにかするしかなかった。結果、納期は守ろうとするあまり、テストがおろそかになり、バグだらけの状態でリリース…なんてことが常だったからな。桧山君も、当初は相当プレッシャーを感じていたと思う」
ちょうどその時、廊下から桧山さんの声が聞こえてきた。駒田部長に今日の進捗を報告しに来たらしい。駒田部長は桧山さんを招き入れた。
「桧山君、ちょうど藤崎さんと君のプロジェクトの話をしていたところだ。今回のプロジェクトは、見事な計画性で進んでいるな。特に、あの初期の厳しい要求に対して、どうやって現実的な計画に落とし込んだんだ?」
駒田部長の問いに、桧山さんは晴れやかな顔で答えた。
「はい、部長。やはりPMOの藤崎さんに、そしてPPMツールに助けられました。正直、当初の要求を見た時は、また厳しい戦いになるだろうと覚悟しました。でも、今回はまず、PPMツール上で徹底的にWBSを作成し、タスクを細分化しました。そして、PMOに教えてもらった過去の類似プロジェクトの工数データと、加藤さんのアドバイスも参考に、現実的な工数を見積もりました」
桧山さんは自信を持って続けた。
「PMOから『無理な計画は品質低下とPMの燃え尽きにつながる』という原則を改めて聞かせてもらい、僕も覚悟を決めて、初期段階で駒田部長や利用部門と再調整の交渉を行いました。PPMツールで具体的な工数とリソースの現状を可視化できたのが、交渉の大きな武器になりましたね。おかげで、無理のないスコープと納期で合意することができました」
藤崎さんは桧山さんの成長を感じ、静かに微笑んだ。ここからは、「火元その3:実現不可能な計画と品質軽視」がプロジェクトをいかに炎上させるのか、そしてPMOがPPMツールを活用し、いかにこの火元を鎮火できるようになったのかを詳しく解説していきます。
実現不可能な計画という名の足かせ
プロジェクトにおいて、初期段階で実現不可能な計画(無理な納期、リソース不足、過剰なスコープ)を立ててしまうことは、プロジェクト全体に大きな足かせをはめることになります。特に、計画の厳しさが品質の軽視に繋がると、その炎上は致命的なものになりかねません。
この火元が引き起こす問題点:
- 品質の著しい低下: 無理な納期を優先するため、テスト期間が削られ、十分な品質確保ができません。結果、リリース後に多くのバグが発覚し、トラブル対応に追われることになります。
- 技術的負債の増大: 短納期に対応するため、場当たり的な実装や設計の妥協が行われ、将来的な保守・運用コストが増大します。
- チームの疲弊と離職: 過度なプレッシャーと長時間労働は、メンバーの心身を疲弊させ、モチベーションの低下や優秀な人材の離職につながります。
- 信用失墜: 約束された品質や機能が提供できないことで、社内関連部署や顧客からの信用を失い、今後のプロジェクトにも悪影響を及ぼします。
PMO主導のPPMツール導入が足かせを外す
駒田部長の回想のように、以前はこのような無理な計画が横行し、多くのプロジェクトが疲弊していました。しかし、PMOが主導でPPMツールを導入し、その活用を推進することで、この「実現不可能な計画」という足かせは外されつつあります。
PMOがPPMツールで実現したこととPMへの支援:
①現実的な計画策定の支援と標準化:
・改善前: 計画策定はPM個人の経験に依存し、非現実的な目標が設定されがちでした。
・改善後: PPMツールに標準的なWBSテンプレートや見積もりロジック、過去のプロジェクト実績データ(工数、品質データなど)を格納し、PMがこれらを参考にしながら現実的な計画を立てられるよう支援します。PMOは、計画策定に関するトレーニングやレビューを実施し、PMが根拠に基づいた計画を立案できるよう後押しします。
②リソース管理の最適化と負荷の可視化:
・改善前: 特定のメンバーに負荷が集中したり、プロジェクト全体のリソース状況が把握しきれていませんでした。
・改善後: PPMツールでプロジェクト横断的なリソース情報を一元管理し、各メンバーの稼働状況やスキルセットを可視化します。PMOは、リソースの偏りやボトルネックを早期に発見し、PMに対して適切な人員配置やタスクの再割り当てを提案。必要であれば、部門間でのリソース調整を支援することで、PMの負荷軽減とチーム全体の生産性向上に貢献します。
③品質管理プロセスの強化と進捗の透明化:
・改善前: 品質管理はテストフェーズに偏りがちで、手戻りが発生する頃には手遅れになることがありました。
・改善後: PPMツールは課題管理機能を通じて、プロジェクトの様々な問題点やリスクを一元的に管理します。また、要件管理やテスト管理は別途専門ツールを活用しますが、PPMツールとの連携により、これらの専門ツールで管理された要件やテストの進捗状況、検出された課題などをPPMツール上で俯瞰し、品質状況の全体像を常に可視化できるよう支援します。 PMOは、これらの品質管理プロセスがツール連携も含めて適切に運用されているかをモニタリングし、早期に品質問題の兆候を検知できるよう支援します。PMは、リアルタイムな品質データを元に、適切なタイミングで対策を講じられるようになります。
④関係者との合意形成と交渉力強化の支援:
・改善前: PMが無理な要求を飲んでしまい、結果的にプロジェクトが破綻することがありました。
・改善後: PPMツールで可視化された客観的なデータ(工数、リスク、リソース状況など)は、PMが関係者(経営層、利用部門など)に対して、現実的な計画の必要性を説明し、合意を形成するための強力な武器となります。PMOは、PMが自信を持って交渉に臨めるよう、データの活用方法や交渉術に関するアドバイスを提供します。
駒田部長のオフィスで、桧山さんは満足げに言葉を締めくくった。
「今回のプロジェクトでは、初期段階でPMOに要件定義の詰め方を指導してもらい、要件管理ツールを活用しつつPPMツールでその進捗を俯瞰的に管理できたことで、初期段階からブレのないスタートが切れました(火元その1の改善)。その上で、チーム内でのコミュニケーションもPPMツールに集約し、情報共有が格段に進みました(火元その2の改善)。だからこそ、今回の計画策定では、PPMツールの過去データやリソース状況を基に、現実的な計画を立て、品質を担保しながら進めることができたんです」
桧山さんの顔には、プロジェクトを無事終えようとしているPMとしての達成感が満ち溢れていた。彼のプロジェクトは、まさにPMOとPPMツールが連携することで、3つの主要な「火元」を全て制圧し、成功へと導かれた好事例となったのだ。
PMOにはプロジェクト内のコミュニケーションの壁を取り払い、PMが孤立することなく、チーム全体でプロジェクトを成功に導くための支援体制を築く役割があります。PPMツールの活用は、その有力な手段となります。
「PMOは見た!」シリーズでは、プロジェクトの健全な運営に役立つ様々なテーマで、引き続き情報をお届けしてまいります。ご期待ください。
【プロジェクト管理に関する情報発信について】
丸文では、効果的なプロジェクト管理に関する実践的な記事やコラムを不定期で掲載しています。記事公開後にメールでの案内を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方は以下のお問い合わせフォームに「Clarityメルマガ配信希望」と記入して送信お願いします。