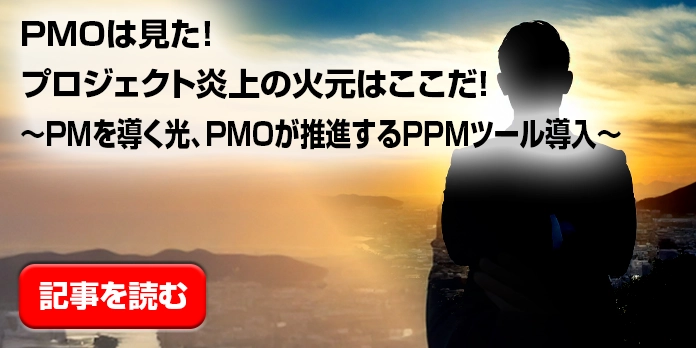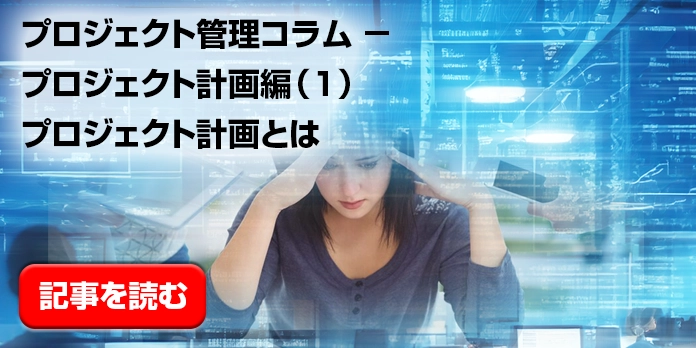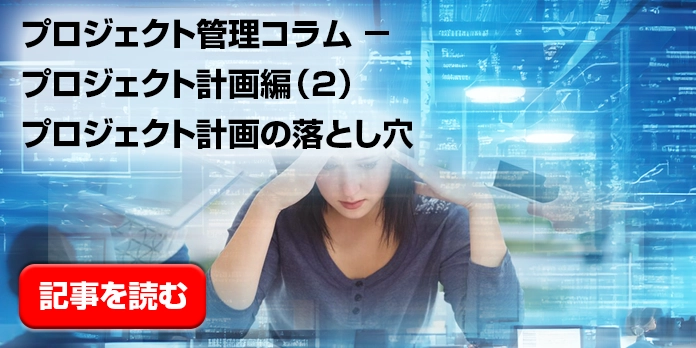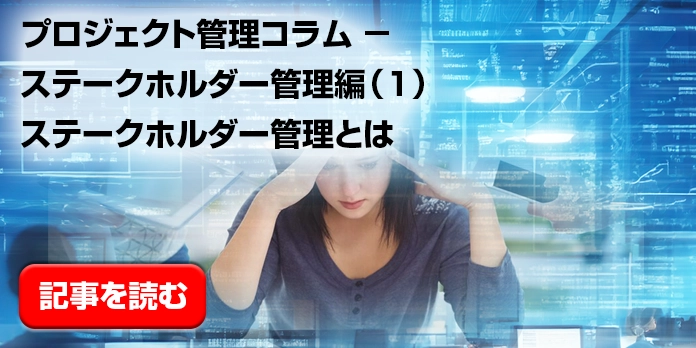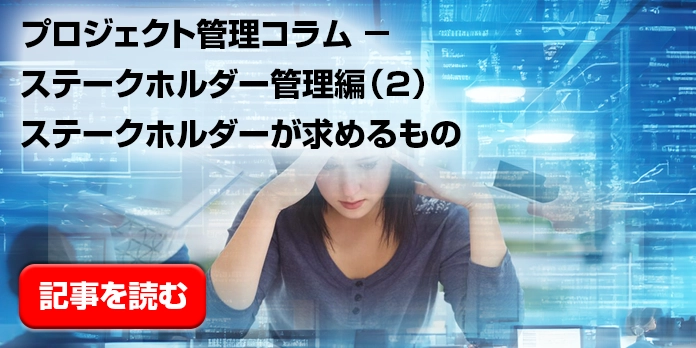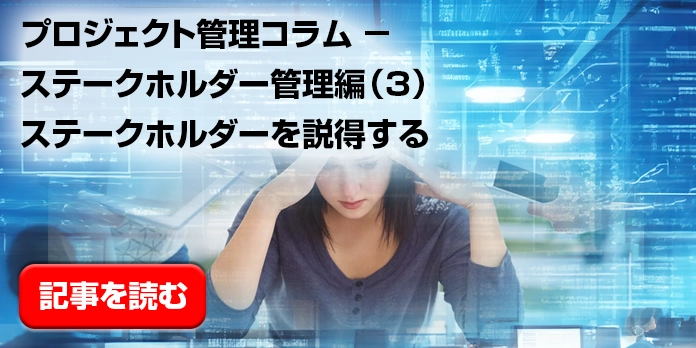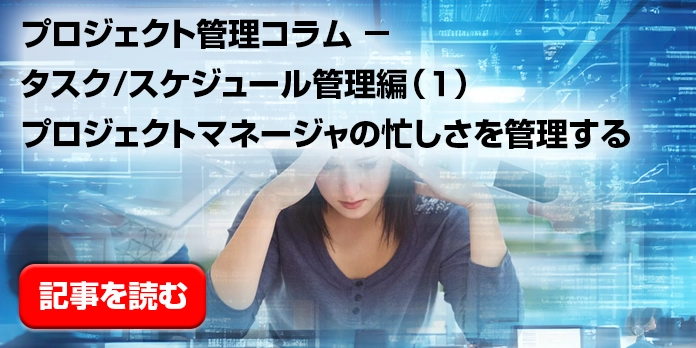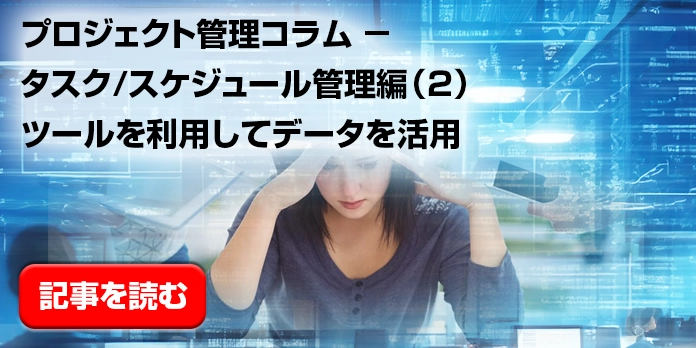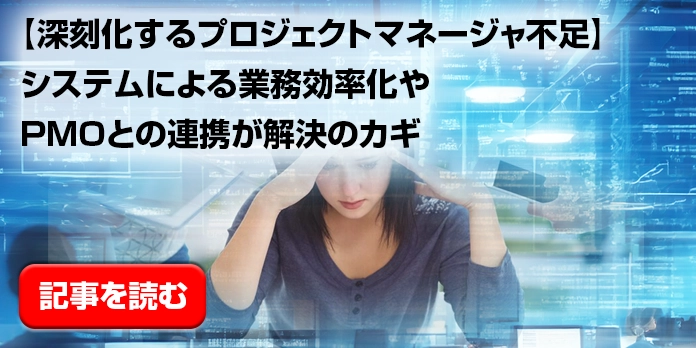PMOは見た!第5回~プロジェクトマネジメントに「生成AI」という名の新チームメイト~
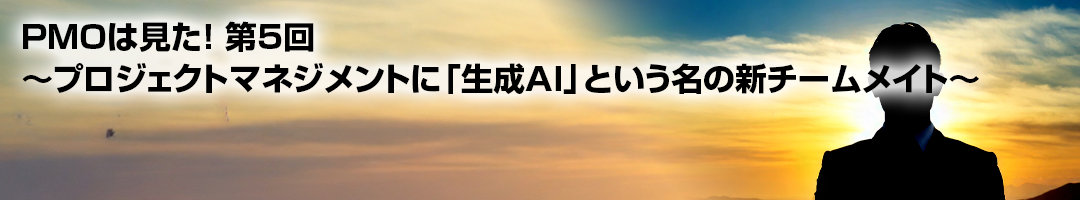
【プロジェクト成功の新たな扉を開く「生成AI」という名の新チームメイト】
PMOとPMの業務に革命をもたらす新チームメイト、「生成AI」の活用術に迫ります。
本記事では、PMOのエキスパートである藤崎さんと開発部門の駒田部長、PMの桧山さんたちの対話を通して、生成AIが日々の複雑な業務をいかに効率化するかを具体的に解説。
PMO室と現場が協力してAI活用を進め、人材不足の課題に立ち向かいながら業務効率と競争力を向上させるストーリー。プロジェクトマネジメントの新たな扉を開く、次世代の働き方をご覧ください。
登場人物紹介
- 藤崎さん: 主人公。PMO室のエキスパート。プロジェクトの課題解決を支援する。
- 駒田さん: 開発部門の部長。組織全体のプロジェクトマネジメント改善を目指している。
- 桧山さん: 開発部門の中堅PM。PMOとPPMツールの支援で成長。
- 加藤さん: 開発部門のベテランPM。桧山さんの指導役として経験に基づいたアドバイスを提供。
「また新しいプロジェクトの計画書をゼロから作らなきゃ」
「この規約について、前にも聞かれた気がするんだけど…」
「なんか最近、あのプロジェクト、雲行き怪しくない?」
——PMとして現場で奮闘する彼らの声が、社内全体のプロジェクトを統括するPMO室まで届く。日々寄せられるそんな声に、どう応えるべきかと考えていた藤崎さんは、開発部門の駒田部長がPMO室に顔を出すのを見て、話しかける。
「駒田部長、最近いかがですか? 以前と比べて、桧山さんのプロジェクトもかなり精度の高い計画が立てられるようになりましたね。PPMツールの導入効果でしょうか?」
駒田部長は頷く。
「もちろんだ。PPMツールのおかげで、リアルタイムな情報共有やリソース管理ができるようになった。だが、藤崎さんのところでは、もう一歩先へ進んでいるのだろう?」
「はい。実は、生成AIという名の新チームメイトが、私たちのチームに加わったようなものです。PMやPMOが向き合う『ちょっと込み入った作業』の効率化に、絶大な効果を発揮しているんですよ」
ちょうどその時、隣のデスクで作業をしていた桧山さんが、会話に気づき、話に加わってきた。
「駒田部長、藤崎さんの言う通りです。僕も最初、半信半疑だったんですけど、本当にすごいんです。つい先日も、AIに助けられました」
桧山さんの顔には、以前のような焦りや疲労の色は全くなく、自信に満ちた、頼もしいPMの顔だ。現場のPMとPMO、双方の課題を解決するAI
「新プロジェクトのキックオフ資料、僕、ゼロから作るつもりだったんです。でも藤崎さんから『過去の類似プロジェクトの資料をAIに学習させてみては?』とアドバイスをもらって。試してみたら、本当にあっという間にドラフトが生成されたんですよ」
【現場PMの「あるある」】
「新しいプロジェクトのキックオフ資料、過去のA案件に似てるから流用しようとしたけど、結局手直しが多くて半日かかっちゃったよ…」
【生成AIでどう変わる?】
過去の計画書や報告書を学習した生成AIが、新しいプロジェクトの情報を入力するだけで、わずか数分でドラフトを自動生成します。PMは修正・加筆に集中できるため、作成時間を大幅に短縮できます。
「しかも、完成した報告書をAIにレビューさせたら、『このKPIの数値、前回の報告と矛盾していませんか?』って、僕が見落としていたミスまで指摘してくれたんです。藤崎さんが最後に確認する前に、自分で品質を上げられる。これ、めちゃくちゃありがたいんです」
隣にいた加藤さんも、深く頷く。
「そうだね、桧山。俺たちベテランPMでも、経験に基づいた勘で気づけることはあるが、大量のデータから矛盾を瞬時に見抜くのは難しいからな。まるで熟練の秘書がチェックしてくれているようだ」
駒田部長は感心した様子で、うなずいた。
「なるほど。計画書や報告書の作成・レビューが効率化されるだけでも、相当な時間短縮になるな」
「ええ。そして、これは私たちPMO側の課題も同時に解決してくれるんです」と藤崎さんが続けた。
PMOの「あるある」を生成AIが解決!
1. 「また同じ質問か…」を「AIが即座に回答」へ:FAQ対応とより広範なサポート
【PMOの「あるある」】
「今日だけで3回も『承認フロー』についての質問が来たな。毎回同じ説明をするのも大変だし、これじゃ他の作業が進まない…」
【生成AIでどう変わる?】
プロジェクト推進規約や標準プロセス、よくある質問とその回答を学習したAIチャットボットが、PMやメンバーからの問い合わせに自動で応答します。PMOは同じ質問に何度も答える手間から解放され、より重要な業務に集中できます。
藤崎さんは言う。「以前は、同じ質問に何度も答えたり、社内規約を探したりするのに時間を取られていました。特に、個別のプロジェクトに常駐する『プロジェクト事務局型PMO』をすべてのチームに配置するのは現実的ではありません。しかし今は、AIチャットボットが瞬時に回答してくれるので、私たちの手が届きにくかったプロジェクトにも、きめ細やかなサポートを行き届かせることが可能になったんです。」
2. 「どこから手をつければ…」を「リスクの兆候をAIが検知」へ:全体把握の精度向上
【PMOの「あるある」】
「部長会で『あのプロジェクトの〇〇、どうなってる?』って聞かれたけど、具体的なリスク兆候って言われると…どこから手をつけていいか…」
【生成AIでどう変わる?】
進捗報告、日々のチャット、議事録など膨大なプロジェクト関連データをAIが常時分析し、PMやPMOが気づきにくい「リスクの兆候」を自動で検出します。さらに、過去事例に基づいた対策オプションも複数提案してくれます。
「あの時、僕のプロジェクトが炎上しそうになったのも、コミュニケーション不足や計画の遅れといった、リスクの兆候に僕自身が気づけていなかったからです。でも今は、AIが『チーム内のコミュニケーション量が低下しています』とか『特定のタスクで遅延傾向が見られます』って警告してくれるので、早めに対策を打てるんです」と桧山さんが付け加える。
藤崎さんは続ける。「これまでは、個々のPMからの報告を待つしかありませんでした。でも今は、AIが常にデータを分析し、リスクを自動検知してくれるので、私たちPMOは会社全体のプロジェクトの状況を、より高精度でリアルタイムに把握できるようになりました」
3. 「分析に時間がかかる」を「深い洞察を即座に提供」へ:レポーティングの自動化と戦略策定
【PMOの「あるある」】
「週次報告会用のデータ集計と分析だけで午前中がつぶれた…肝心な『なぜこうなっているのか』を掘り下げる時間が足りない!」
【生成AIでどう変わる?】
プロジェクトの進捗データやKPIを生成AIが自動で深く分析します。「このプロジェクトは目標達成率が高いが、リソースの特定部分に偏りが見られる」「品質指標が低下傾向にあるのは、〇〇フェーズでのレビュー不足が原因である可能性が高い」といった、人間が見つけにくい傾向やボトルネックをAIが発見し、分かりやすく提示してくれます。
「毎週の週次報告会でも、集計にかかる時間が激減した。その分、皆で『なぜこうなっているのか』を議論する時間に充てられるようになったんだ。より本質的な課題解決に集中できるようになった」と加藤さんが語る。
藤崎さんは強調する。「私たちPMOも、以前は各プロジェクトのレポート作成に多くの時間を費やしていました。今は、AIが自動でレポートを作成してくれるので、その分、会社全体のプロジェクトポートフォリオを分析し、より戦略的な改善策を立案するなど、付加価値の高い業務に時間を割けるようになったのです」
蓄積されたデータと進化するAIが拓くPMOの未来
「藤崎さんの話を聞いていて、気づいたことがある。以前の私は、炎上したプロジェクトをなんとか立て直すことで精一杯だった。だが、この生成AIという名の新チームメイトの仕組みは、そうなる前に防ぐことを可能にしてくれる。PMOの仕事の範囲が、より上流に広がっていくということだな」と駒田部長が言った。
「その通りです。そして、ここ数年の生成AIを含むAI関連技術の進歩はすさまじく、私たちもPPMツール導入時点では考えもしなかったことが、次々と実現しています。」と藤崎さんは続けます。
「PMO業務におけるAI活用は、もはや単なる効率化のツールではありません。現在、すでにAI技術の活用が進んでいる会社とそうでない会社とでは、業務効率に大きな差がつき、それがそのまま競争力の差になりつつあります。 また、人材採用が難しい中、生成AIは経験豊富なアシスタントを何人も雇うのに匹敵する効果をもたらしてくれます。これにより、各PMがより少ないリソースで高い成果を出すことが可能になり、組織全体の生産性が飛躍的に向上するのです。」
「これからもAI技術はどんどん発展していきますが、PPMツールによって日々の活動データがきちんと蓄積されていれば、私たちはそうした新しい技術を速やかに活用し、プロジェクトマネジメントをさらに進化させることができます。」
駒田部長は神妙な面持ちで藤崎さんを見つめます。
「しかし、まだ活用しているのは一部のPMだけだろう? どうすれば、この新しいチームメイトを全社に広められるだろうか?」
藤崎さんは力強く答えます。「そのために、駒田部長のような管理職の方々が率先してその価値を認め、活用を促すことが何よりも重要です。 現場のPMが『使ってみなさい』と言われるだけでなく、『部長も使っているのか』と実感できる環境を作る。例えば、週次の部内会議の報告資料をAIに作成させたり、AIが自動で提示したリスク分析結果を議題に取り上げたりするのです。私たちは、そのための成功事例や利用ガイドを準備し、トップダウンとボトムアップの両方から浸透を図っていきます。」
駒田部長は藤崎さんの提案にハッとさせられたように顔を上げます。
「なるほど。そうか、私がやってみればいいのか。よし分かった、じゃあちょっと教えてもらえるかな」
藤崎さんの顔に、確信に満ちた笑みが浮かびます。
「もちろんです。駒田部長のお時間を少しいただけますか? 具体的にどの業務からAIを活用していくのが最も効果的か、一緒に考えていきましょう。」AIは、プロジェクトの成功確率を高め、PMOがより戦略的な活動に集中できる環境を創出します。
もちろん、AIはあくまでツールであり、最終的な判断は人間のPMOやPMが行うべきです。しかし、AIが複雑な業務を強力に支援することで、人間はより創造的で、本当に価値のある仕事に集中できるようになります。
これまで「PMOは見た!プロジェクト炎上」シリーズとして、プロジェクトの火元を消す話をしてきました。しかし、これからは、AIが未然に火元を制圧するのが当然になり、炎上なんて起こらない未来が来るかもしれませんね。
【プロジェクト管理に関する情報発信について】
丸文では、効果的なプロジェクト管理に関する実践的な記事やコラムを不定期で掲載しています。記事公開後にメールでの案内を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方は以下のお問い合わせフォームに「Clarityメルマガ配信希望」と記入して送信お願いします。